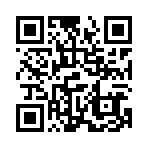2025年04月27日
104歳の生きる姿に感銘!
今日は、前から見たいと思っていた「104歳、哲代さんのひとり暮らし」というドキュメンタリー映画を見に行った。まず感じたのは、とにかく哲代さんがユーモア精神あふれ、明るくて楽しい!!ということ。そして年を重ねていく中でできなくなってしまうことでもプラス思考に変えて行動する姿勢。例えば家の前の急な坂道。その坂を上ったり下りたりするのがだんだん大変になってくる。特に下りは大変。そんななか、哲代さんは、くるりと後ろ向きになり、杖を突きながら、一歩一歩ゆっくりと歩いておりていく。すぐにできない!と嘆くのではなく、できる方法を機転を利かして見つけ出す。素晴らしい!そして小学校の先生だった哲代さんが、米寿になった教え子たちと再会するシーンでは、哲代さんは素直に涙する。とても自然体の姿が胸をつく。大きな声で皆で唱歌を歌うときには、リズミカルに両手で音楽に合わせ指揮をとり、口を縦にして一番大きな声で楽しそうに歌う。米寿の教え子たちよりももっと元気な哲代さんには頭が下がる。すべての場面で哲代さんの生きる姿に感銘を覚える。そして入退院をする中で、「お家が一番落ち着く」という言葉。夫と二人で自分たちで建てた家、仏様、墓守もしっかりせんと、という言葉もとても印象的だった。周りの人たちやご先祖様、だれにでもいつも感謝の気持ちを忘れない哲代さん。哲代さんの生きる姿は、わたしにたくさんのパワーをくれた!
2024年12月29日
我が家の10大ニュースに家族の歴史を感じる!
今日は、次女が自宅に来たので、夕食後、皆で恒例の「我が家の10代ニュース」を書きだしまとめてみた。このしきたり(‽?)はドイツに行った2000年、つまり24年前から家族皆が集まり、意見を出し合って決めている。娘たちがまだ子どもだった時と違い、今は、なかなか家族全員が集まることは難しくなりつつあるが、参加できない時は、ラインや電話などで意見を聞いてまとめている。皆で2000年から今までの主なニュースを振り返り、あのときは、こうだったねー、と話がはずむ。ドイツ生まれの我が家の愛犬だったブラッキーに関するニュースもたくさん!
2001年、ブラッキー我が家に来る
2002年、ブラッキー肉球を切り手術
2003年、ブラッキー初めてペンションに預ける
2004年、ブラッキー脱走してTierheimに保護される~そして2015年、ブラッキーが天国に行くまでのニュースが綴られている。
ブラッキー、そして我が家の歴史がここにある!

ドイツの家のbathroomの窓からブラッキーと一緒に仕事に出かける相棒を見送る娘。
2001年、ブラッキー我が家に来る
2002年、ブラッキー肉球を切り手術
2003年、ブラッキー初めてペンションに預ける
2004年、ブラッキー脱走してTierheimに保護される~そして2015年、ブラッキーが天国に行くまでのニュースが綴られている。
ブラッキー、そして我が家の歴史がここにある!

ドイツの家のbathroomの窓からブラッキーと一緒に仕事に出かける相棒を見送る娘。
2024年09月28日
人生後半の自分と向き合う!
今日は、「臨床心理学から見た人生の後半への向き合い方」という講演会に行ってきた。講演では、人生の振り返りということで自分史を書くことの勧め、そして死の受容についても触れられた。以前、自分史を書くというセミナーがあるのを目にしたことがあるが、あまり関心を持っていなかったが、年齢を重ねるにつれて、ふと自分の今までの人生を一度じっくり振り返るのも良いかなと思った。講演では、自分史を書くことにより、自分のライフストーリーを振りかえり、それを意識化することで意味をもってくるというお話しだった。確かに自分の博論では、ライフストーリーという手法を用い、たくさんの人々にインタビューをお願いしたが、皆、一堂に、語ることで今までの自分の生き方を振り返ることができて、新鮮な気持ちになれたという感想をいただいた。ライフストーリーを語ったり、記したりすることで、そこに意味や意義が生じるのであろう。そしてそれが、これからの自分の人生につながっていく。講演の中でも自分史を書くことは、「次にライフステージへの転換」というお話もあったが、それは年を重ね、避けられない「死」にちかづくなかでも大変大きな意義を持つのかもしれない。さらに講演の最後に講演者は、昨年死去した大江健三郎の最後の作品『晩年様式集』からの文章を引用し、大変印象的なことばだと述べた。
「小さなものらに、老人は答えたい、私は生き直すことができない。しかし、私らは生き直すことができる」
個人的には、まだこの作品は読んだことがないのだが、この「私ら」は、一体だれを表わしているのであろうか。次世代?新たに生まれてくる命?すくなくともこの言葉から私は、「死」というものがその人の終わりではなく、これから先も何らかの形で繋がっていく、という明るい未来への希望を感じることができた。是非、この作品を読んでみたいと思う。自分としっかり向き合っていくステージがやってきたように感じる。

Grand Canyonのsun rise!500万~600万年という時間をかけて作り上げられた渓谷。大自然の力に驚くばかり!
「小さなものらに、老人は答えたい、私は生き直すことができない。しかし、私らは生き直すことができる」
個人的には、まだこの作品は読んだことがないのだが、この「私ら」は、一体だれを表わしているのであろうか。次世代?新たに生まれてくる命?すくなくともこの言葉から私は、「死」というものがその人の終わりではなく、これから先も何らかの形で繋がっていく、という明るい未来への希望を感じることができた。是非、この作品を読んでみたいと思う。自分としっかり向き合っていくステージがやってきたように感じる。

Grand Canyonのsun rise!500万~600万年という時間をかけて作り上げられた渓谷。大自然の力に驚くばかり!
2024年09月19日
義務的退職制度を考える!
長い夏休みも終わり、いよいよ明日から大学が始まる。たった今、授業の最終準備を終えたところ。何年授業をしていてもやはり前日は緊張する。履修名簿を見ながら、どんな学生たちが来るのか、楽しみでもある。通年の学生たちは、どんな夏休みを過ごしたのだろうか。彼らはまた前期とは違った顔を見せてくれる。私にとり、仕事というのは、良い意味でのストレス、そして生活や人生に張り合いを与え、社会とつながっていることを実感させてくれる。年を重ねていく中でいつまで仕事を通して社会とつながっていられるのか、ふと思うこともあるが、元気な間は、何らかの形でできるだけ仕事は続けていきたい。先日、米国では義務的退職制度が撤廃されたという旨の新聞の記事を目にした。そしてその記事の著者、ジャレド・ダイアモンド氏は、義務的退職制度は、「人々から社会的交流や人生の目的、自分が有益な存在だと思える理由を奪ってしまう」と述べている。私も同感である。もちろん、人によっては、定年が待ち遠しかったり、仕事以外にも生きがいを感じることもあるであろう。しかし、元気でやる気のある高齢者にとって、日本の強制的な義務付けられた定年制度は、そのような人びとの人生にマイナス面もたらすのではないのだろうか。知り合ったある女性は、「まだまだ仕事をしたいのに、70歳になったらやめなきゃいけないのよね」と残念そうに言っていた。高齢者たちがいつまでも残ると若者たちの仕事を奪う側面もある、とも言われているが、今一度、義務的退職制度について顧みてみることも大切だと思う。ダイアモンド氏の「私たちのような、働く高齢の米国人は、人生と仕事、米国社会への貢献を楽しんでいる」という言葉には、うらやましさを感じた。実際にダイアモンド氏は86歳で大学教授を「引退」し、これからは自由な時間を執筆活動に充てるという。

サンフランシスコの楽しいパン屋さん‼作りたてのパンがかごに入ってロープ伝いに売り場まで送られてくる!!

サンフランシスコの楽しいパン屋さん‼作りたてのパンがかごに入ってロープ伝いに売り場まで送られてくる!!
2024年06月08日
病気は神様からの贈り物!
今日の夕刊に「病気を神様からの贈り物として受け入れ、前向きに生きる人」として緑内障患者のカメラマンの男性が紹介されていました。この男性は以前にも新聞の医療関係の記事にも取り上げられていて、気になっていました。若い時に緑内障と診断され、会社の仕事を辞めてカメラマンになったのですが、緑内障だからこそ見える世界、「多重露光」というやり方を駆使し、独自の作品を撮られているとのこと。そしてその「独特の世界観」をもつオリジナリティの作品が国内外で評価されていると記されていました。本人の「緑内障はつらい。でも、緑内障になったからこそ今の生き方ができているし、自分にしかできない表現ができるようになりました」という言葉は、とても心に残りました。年齢を重ねていくと体にいろいろな変化が起き、辛かったり、痛かったり、病気になったり、いろいろな症状が出てくるでしょう。でもそれをどのように受けとめるかによっても前向きに生きることができる!そんな勇気をこの男性からもらいました。
2024年01月07日
学びは、一生続く!
今日は、夫の元上司のお宅にお年賀に行きました。その時に丁度、上司のお姉さんにお会いできて、少しお話をしたのですが、今は大学を退官なさっていて、退官後も研究を続け、執筆活動をなさっているとのことでした。ご専門は教育心理学で特に学習に困難をきたす子どもたちに焦点を当てた研究を続けていらっしゃいます。そして昨年、執筆なさったという著書をくださいました。その本には、研究によると過去には、LD(学習機能不全/不調)は治癒できず対処あるのみと言われ、自分自身もそのように受け止めていたが、その考えを訂正することがこの書の目的であるとありました。つまり、現時点では、「神経可塑性」という能力により、治癒可能であるということです。今まで自分が述べてきたことを新たな知識や理論を得ることにより、訂正し、そのことを多くの人に伝えたいという姿勢に頭が下がります。私の所属する研究会も退官なさった先生が始められたものですが、常に若手研究者たちも交え、ご自分の研究を深められていらっしゃいます。今回の出会いも含めて、学びは一生続けることができる、そして少しでも学びから得た知識や理論、経験を社会に還元し、それが誰かの幸せにつながっていったらいいなと思いました。

これは、artistのフランス人の友が手作りして送ってくれたものです。娘の4か月児のために丁寧に作ってフランスから送ってくれました。彼女は今も息子夫婦の小さな孫たちのお世話をしながら、芸術活動を続けています。そして彼女の学びや経験が、しっかりと誰かにとり幸せにつながっています!少なくとも私たちにとって!

これは、artistのフランス人の友が手作りして送ってくれたものです。娘の4か月児のために丁寧に作ってフランスから送ってくれました。彼女は今も息子夫婦の小さな孫たちのお世話をしながら、芸術活動を続けています。そして彼女の学びや経験が、しっかりと誰かにとり幸せにつながっています!少なくとも私たちにとって!
2023年10月05日
「考える」ということ
先月9月20日に社会学者の加藤秀俊さんが93歳で亡くなりましたが、加藤さんについて、社会学者の竹内洋さんは、「私たちは、先生(加藤秀俊さん)の著作から事実を通して自分の頭で思索するとはどういうことなのかに思いをはせることができる」と記しています。確かに今は、インターネットなどをとおして、情報が簡単に入手でき、それを事実として鵜呑みにしがちです。私自身もわからないことがあると、自分で考えることもせず、すぐにネットで検索することが多くなりました。ましてや時間に追われる日々の中では安易に答えをもとめがちです。竹内さんによると、加藤さんは著書の中で「与えられた知識のうえに生きることがあまりにも多く、ゆるぎない事実を通して思索することがあまりにすくない」ことを指摘されています。とても重い言葉だと思います。たまたま、今日、聞いていた英語のニュース番組で、”イグ・ノーベル賞”日本人が受賞、というトピックを扱っていました。そのニュースのなかに次のような内容がありました。
The parody award was started in an American science journal in 1991 to celebrate quirky research that "makes people laugh, then think."
この賞は、「人々を笑わせ、それから考えさせる奇抜な研究」ということですが、これらの研究は、とてもユニークな発想で、私たちを笑わせ、そして、ふと立ち止まらせ、考えさせてくれるものだと思います。このような楽しい素晴らしい発想が出てくるのは、日々、目に入り、耳にする知識や情報をcriticalに捉える姿勢が基本にあるからだと感じました。自分自身もそのような姿勢をみならいたいものです。

近くの公園で見つけた銅像。「考える」時間をもつこと、大事ですね!「わからないこと」も「わからないまま」も楽しむことも!
The parody award was started in an American science journal in 1991 to celebrate quirky research that "makes people laugh, then think."
この賞は、「人々を笑わせ、それから考えさせる奇抜な研究」ということですが、これらの研究は、とてもユニークな発想で、私たちを笑わせ、そして、ふと立ち止まらせ、考えさせてくれるものだと思います。このような楽しい素晴らしい発想が出てくるのは、日々、目に入り、耳にする知識や情報をcriticalに捉える姿勢が基本にあるからだと感じました。自分自身もそのような姿勢をみならいたいものです。

近くの公園で見つけた銅像。「考える」時間をもつこと、大事ですね!「わからないこと」も「わからないまま」も楽しむことも!
2023年09月14日
自分らしく生きる:人生の先輩たちから学ぶ
今日は、訪問リハビリテーションをなさっている作業療法士の方のお話しを聞く機会がありました。その中で、印象に残った言葉は、心身機能に何か障害があった場合、その回復を求めすぎるのではなく、その人らしい生活を維持することがとても大切、というものでした。私たちは、何か問題があると、その回復を目指しがちですが、大事なのは、その問題や障害と向きあい、時にはそれらを受け入れ、その中で自分らしく生きていくという事。確かに年を重ねていくと、今までのように機敏に動けなかったリ、体力の低下を感じたり、集中力に欠けたり…自分の中でも変化を感じることがあります。その時に若い時と同じような自分を目指すのではなく、うまく対処して、というより、むしろそれを楽しむという向き合い方も面白いかもしれません。若い時と違う自分、変わっていく自分、を客観的に観察しながら。そして、自分より年上の方々といろいろ話をすることもとても刺激的で勉強になります。心身機能が変化していくなかで、どのような形で折り合いをつけながら、自分らしく暮らしていくのか。これからも人生の先輩たちとつながり、さまざまのことを学びたいと思っています。

ケープタウンのレストランで食べた魚介類盛り合わせ。食欲だけは年をかさねても減らない??

ケープタウンのレストランで食べた魚介類盛り合わせ。食欲だけは年をかさねても減らない??
2023年04月26日
失敗から学ぶ新たな挑戦!
Hi, everyone! It was very chilly today, wasn't it?
今日の新聞記事に、日本の宇宙企業アイスペースが、世界で民間企業初となる月着陸を目指していたが、その目標が達成できなかった、とありました。私も是非成功したらよいなと希望を持っていたので、とても残念に思いました。でも、そのあとに、創業当初から技術面で支えてきた東北大学の吉田教授の「失敗なくして成功はない。今回得られた教訓やデータを生かし、挑戦を続けて欲しい」という言葉を目にして、なんだかとてもジーンときました。私自身、今まで、失敗することが怖くて、二の足を踏むことがありました。確かに失敗をあまりしたくない、できるだけ避けたいと思いがちですが、失敗から学ぶことはとても多いと思います。また、「失敗」ではないですが、大学の語学の授業において、学生たちは、間違うことを恐れて、どうも完璧な正しい英語を話すことに重きをおきがちです。ですから、わたしからはいつも「間違いを恐れることはない。むしろ、たくさん、間違いをしてください! 間違えたら、それを直していけばよいのです。ただそれだけのことです。」と伝えています。学生にそのようなメッセージを送っている私ですが、なんと、どうやら失敗や間違いを恐れている自分がいるようです。吉田教授の言葉を目にして、これからは、失敗や間違いを恐れず、そこから学んでいこう、それが成功につながるんだ、という意識を持ち続けようと強く思いました。
今日の新聞記事に、日本の宇宙企業アイスペースが、世界で民間企業初となる月着陸を目指していたが、その目標が達成できなかった、とありました。私も是非成功したらよいなと希望を持っていたので、とても残念に思いました。でも、そのあとに、創業当初から技術面で支えてきた東北大学の吉田教授の「失敗なくして成功はない。今回得られた教訓やデータを生かし、挑戦を続けて欲しい」という言葉を目にして、なんだかとてもジーンときました。私自身、今まで、失敗することが怖くて、二の足を踏むことがありました。確かに失敗をあまりしたくない、できるだけ避けたいと思いがちですが、失敗から学ぶことはとても多いと思います。また、「失敗」ではないですが、大学の語学の授業において、学生たちは、間違うことを恐れて、どうも完璧な正しい英語を話すことに重きをおきがちです。ですから、わたしからはいつも「間違いを恐れることはない。むしろ、たくさん、間違いをしてください! 間違えたら、それを直していけばよいのです。ただそれだけのことです。」と伝えています。学生にそのようなメッセージを送っている私ですが、なんと、どうやら失敗や間違いを恐れている自分がいるようです。吉田教授の言葉を目にして、これからは、失敗や間違いを恐れず、そこから学んでいこう、それが成功につながるんだ、という意識を持ち続けようと強く思いました。
2023年04月06日
「生きることなく、人生を終えたくない」
Hi, everyone! How are you doing?
今日は、前から見たいと思っていた「生きる Living」という映画を見ました。ノーベル賞作家のカズオ・イシグロが脚本を担当、そして黒澤明監督の「生きる」のリメイクということもあり、とても関心がありました。第2次世界大戦終結から数年後のロンドンを舞台にしたもので、お役所に勤める公務員の男性、ウィリアムズが主人公です。ある日、がんで余命が短いということを宣告され、人生を見つめ直し、生きるとは何かを問いかけていきます。そして、人生を見つめ直し、生まれ変わっていくのです。自分の中で答えを出した彼に、仕事への取り組み方、職場や他の人々とのつながり方一つをとっても、生命力がみなぎっていくのが伝わってきます。人は、何てこんなに生き生きと生きることができるのだろう。感銘しました。主人公がまるで別人のように変わっていくのをみながら、自分の中の気持ちもだんだんと熱くなってくるのを感じました。そして、ウィリアムズの言葉で一番記憶に残ったのは、「生きることなく、人生を終えたくない」というものです。この言葉は、とても深い意味を持っていると思います。「生きる」とは何か。「生きる」とは、ただ単に息をして体が生きているというだけではなく、もっと強いパワー、生命力、力強さを供え合わせているように思います。私も、ウイリアムズのように「生きる」とは何か、今一度しっかりと考え、これからの人生を「生きて」いこうと気持ちを新たにしました。

花びらが散った葉桜に生命力を感じます。
今日は、前から見たいと思っていた「生きる Living」という映画を見ました。ノーベル賞作家のカズオ・イシグロが脚本を担当、そして黒澤明監督の「生きる」のリメイクということもあり、とても関心がありました。第2次世界大戦終結から数年後のロンドンを舞台にしたもので、お役所に勤める公務員の男性、ウィリアムズが主人公です。ある日、がんで余命が短いということを宣告され、人生を見つめ直し、生きるとは何かを問いかけていきます。そして、人生を見つめ直し、生まれ変わっていくのです。自分の中で答えを出した彼に、仕事への取り組み方、職場や他の人々とのつながり方一つをとっても、生命力がみなぎっていくのが伝わってきます。人は、何てこんなに生き生きと生きることができるのだろう。感銘しました。主人公がまるで別人のように変わっていくのをみながら、自分の中の気持ちもだんだんと熱くなってくるのを感じました。そして、ウィリアムズの言葉で一番記憶に残ったのは、「生きることなく、人生を終えたくない」というものです。この言葉は、とても深い意味を持っていると思います。「生きる」とは何か。「生きる」とは、ただ単に息をして体が生きているというだけではなく、もっと強いパワー、生命力、力強さを供え合わせているように思います。私も、ウイリアムズのように「生きる」とは何か、今一度しっかりと考え、これからの人生を「生きて」いこうと気持ちを新たにしました。

花びらが散った葉桜に生命力を感じます。