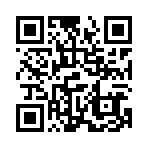2011年11月30日
ドイツではありえない心憎い程の日本の気遣い!!
今日は本当に感激した日だった!!
お店でお風呂用のふたカバーを買ったのだが、かなり重かったので、売り場で「電車やバスに乗るので、持ちやすいようにしてください。」とお願いした。きっとひもで結わいて、持ちやすいように取っ手でもつけてくれるのかなと思っていたら、案の定そのようにしてくれた。そしてその取っ手を持った瞬間に「感激!!」なんとその「取っ手」によく引っ越しの時などに壊れ物を包むプチプチがちゃんとつけられていたのだ!!そのプチプチがついているため重いものを持っていても取っ手に指がくい込むような感触は全くなくふわふわしてとても楽だ。本当にちょっとしたことなのだが、こんな「気遣い」は、ドイツではありえない。全く心憎いばかりだ!!!
こんな素敵な「気遣い」のおかげで今日は1日いい気持ちで過ごせた!!
私もなにげない小さな「気配り」・「心配り」を心がけていこうと思った。
お店でお風呂用のふたカバーを買ったのだが、かなり重かったので、売り場で「電車やバスに乗るので、持ちやすいようにしてください。」とお願いした。きっとひもで結わいて、持ちやすいように取っ手でもつけてくれるのかなと思っていたら、案の定そのようにしてくれた。そしてその取っ手を持った瞬間に「感激!!」なんとその「取っ手」によく引っ越しの時などに壊れ物を包むプチプチがちゃんとつけられていたのだ!!そのプチプチがついているため重いものを持っていても取っ手に指がくい込むような感触は全くなくふわふわしてとても楽だ。本当にちょっとしたことなのだが、こんな「気遣い」は、ドイツではありえない。全く心憎いばかりだ!!!
こんな素敵な「気遣い」のおかげで今日は1日いい気持ちで過ごせた!!
私もなにげない小さな「気配り」・「心配り」を心がけていこうと思った。
タグ :ドイツと日本
2011年11月29日
失われていく日本の食伝統??
最近至る所で「おせち」の予約案内を目にする。
私がドイツに行った11年前は、身の回りに、こんなにたくさんの広告や案内はなかったような気がする。久しぶりに日本に戻り、「おせち」の案内や広告の多さにはビックリ。
実際にどのくらいの人がおせちを自分の家で用意せず、注文するのかはわからないが、少なくとも昔は、各家庭でおせちの準備をしていたように思う。私の家でも母が、お煮しめや黒豆、きんとんなど煮て、きれいにお重に並べていたことを思い出す。
私も日本にいる間はあまり自分では作らず出来合いの栗きんとんやかまぼこ、お豆などお店で買っていたが、おせちの材料を買いにに師走のにぎやかな商店街に行くのも楽しいし、きれいにお重に並べる時もお正月がもうじき来る嬉しさが感じられる。確かに注文するのは簡単だが、何だかさびしいような味気ないような気がする。
更には「洋風おせち」なども目にし、ローストビーフやミートローフなどもお重に入っているようだ。
おせち料理は、レンコン、昆布巻きなどそれぞれが新年を祝う心を表すもので意味がある。日本の素晴らしい食伝統を失ってしまうのはとても残念に思う。
ドイツにいる間は、「おせち料理」が食べたくなり、注文することもできたが、あまりにも高かったので、せいぜい、かまぼこや黒豆を買ったぐらいかな。ドイツ生活が長くなり、どうしてもおせち料理がいただきたい場合はオランダのある日系のホテルに行きそこでおせちを頂くこともできた。海外に長ければ長いほど、日本の物が懐かしくなる。そういう私も「和菓子」が無性に食べなくなり困ったこともある。日本に一時帰国の時には、美味しい「和菓子」がいただけ本当に幸せに感じたことを思い出す。
日本にいるとあまりありがたみや素晴らしさに気が付かないが、美しい和菓子や深い意味を持つ「おせち料理」、日本の食の伝統も大切にしていきたいと思う。
私がドイツに行った11年前は、身の回りに、こんなにたくさんの広告や案内はなかったような気がする。久しぶりに日本に戻り、「おせち」の案内や広告の多さにはビックリ。
実際にどのくらいの人がおせちを自分の家で用意せず、注文するのかはわからないが、少なくとも昔は、各家庭でおせちの準備をしていたように思う。私の家でも母が、お煮しめや黒豆、きんとんなど煮て、きれいにお重に並べていたことを思い出す。
私も日本にいる間はあまり自分では作らず出来合いの栗きんとんやかまぼこ、お豆などお店で買っていたが、おせちの材料を買いにに師走のにぎやかな商店街に行くのも楽しいし、きれいにお重に並べる時もお正月がもうじき来る嬉しさが感じられる。確かに注文するのは簡単だが、何だかさびしいような味気ないような気がする。
更には「洋風おせち」なども目にし、ローストビーフやミートローフなどもお重に入っているようだ。
おせち料理は、レンコン、昆布巻きなどそれぞれが新年を祝う心を表すもので意味がある。日本の素晴らしい食伝統を失ってしまうのはとても残念に思う。
ドイツにいる間は、「おせち料理」が食べたくなり、注文することもできたが、あまりにも高かったので、せいぜい、かまぼこや黒豆を買ったぐらいかな。ドイツ生活が長くなり、どうしてもおせち料理がいただきたい場合はオランダのある日系のホテルに行きそこでおせちを頂くこともできた。海外に長ければ長いほど、日本の物が懐かしくなる。そういう私も「和菓子」が無性に食べなくなり困ったこともある。日本に一時帰国の時には、美味しい「和菓子」がいただけ本当に幸せに感じたことを思い出す。
日本にいるとあまりありがたみや素晴らしさに気が付かないが、美しい和菓子や深い意味を持つ「おせち料理」、日本の食の伝統も大切にしていきたいと思う。
タグ :日本の食伝統
Posted by ゆっこ at
23:54
│Comments(0)
2011年11月29日
ドイツでの美術館の楽しみ
ドイツにいる間、よく美術館にでかけた。私がいたデュッセルドルフには近代美術館、州立美術館などいくつかの美術館があるが、人混みで作品がよく見られないということはない。
日本では特に東京では「絵画」を見るのではなくて「人」を見に行くようで、あまり美術館に足を運ぼうという気になれない。
ましてロープ規制があり、絵画を近くで見られないということもドイツではない。本当に近くに行って見たりいろいろな角度からじっくり作品を鑑賞できる。また、私が一番好きなカフェも充実している。絵画鑑賞に疲れたら、カフェでほっと一息つくことも大きな楽しみだ。
更に感激したのは、デュッセルでは、"Nacht der Museen"といってオールナイトで様々な美術館をはしごできる日があるのだ。各美術館の移動にもシャトルバスが運行され便利だ。また、通常は4月下旬の季節のいい時なので館内だけでなく屋外でもライブバンドが入ったりして音楽も楽しめる。
美術館は絵画だけでなくその空間や雰囲気も楽しめるようになっていて、市民の生活の中に上手に溶け込んでいるような気がした。
日本の美術館ももっと身近になり、かつ「絵画鑑賞」目的だけでなく、美術館のかもし出す独特な雰囲気も楽しめるような空間が演出されたらもっと美術館に行くのが楽しくなるのにと思う。
日本では特に東京では「絵画」を見るのではなくて「人」を見に行くようで、あまり美術館に足を運ぼうという気になれない。
ましてロープ規制があり、絵画を近くで見られないということもドイツではない。本当に近くに行って見たりいろいろな角度からじっくり作品を鑑賞できる。また、私が一番好きなカフェも充実している。絵画鑑賞に疲れたら、カフェでほっと一息つくことも大きな楽しみだ。
更に感激したのは、デュッセルでは、"Nacht der Museen"といってオールナイトで様々な美術館をはしごできる日があるのだ。各美術館の移動にもシャトルバスが運行され便利だ。また、通常は4月下旬の季節のいい時なので館内だけでなく屋外でもライブバンドが入ったりして音楽も楽しめる。
美術館は絵画だけでなくその空間や雰囲気も楽しめるようになっていて、市民の生活の中に上手に溶け込んでいるような気がした。
日本の美術館ももっと身近になり、かつ「絵画鑑賞」目的だけでなく、美術館のかもし出す独特な雰囲気も楽しめるような空間が演出されたらもっと美術館に行くのが楽しくなるのにと思う。
タグ :ドイツの美術館
2011年11月28日
交通渋滞のないドイツ?
今日の夕方、ラジオで「高速道路が日帰り観光の帰りで51キロの渋滞」というような交通情報を聞いた。その時ふとドイツのことを思い出した。
ドイツに渋滞がないと言ったらうそになるが、10年間のドイツ滞在中、日本のような何十キロというひどい渋滞に巻き込まれたことはない。もちろん、交通事故や道路の工事で3車線が2車線や1車線になったときなどは渋滞になるが、通常あまり気にならない。
日本で「渋滞」が一番よく話題になるのが、お盆のころの帰省ラッシュや都心へのUターンラッシュだが、ドイツでは夏休みに車で出かけても大変な思いをしたことはない。大きな理由の一つとしてはドイツの各州それぞれが違った期間、学校の休みになっているからだと思う。来年に関して言えばたとえば、夏休みは、私の住んでいたNordrhein-Westfalen州は、7月9日から、8月21日まで、そして南のBayern州は、8月1日から、9月12日までとなる。それぞれの州で、イースター休み、夏休み、秋休み、冬休みの期間が違っている。よく考えられていると思う。
そして、とにかくうれしいことは凸凹がなく道がとてもよく整備され、アウトバーンがすばらしいのだ。制限速度がないのだから、時速200キロぐらい出している車も目にする。
ドイツからオランダ、フランス、オーストリアなどに車で移動するとすぐに制限速度の標識が出てくるし、道が悪くなるのが体感できる。
更にうれしいことは、ドイツには料金所がなく通行料を支払わなくてもよいことだ。
ドイツ国内の車の旅がなつかしい!!
ドイツに渋滞がないと言ったらうそになるが、10年間のドイツ滞在中、日本のような何十キロというひどい渋滞に巻き込まれたことはない。もちろん、交通事故や道路の工事で3車線が2車線や1車線になったときなどは渋滞になるが、通常あまり気にならない。
日本で「渋滞」が一番よく話題になるのが、お盆のころの帰省ラッシュや都心へのUターンラッシュだが、ドイツでは夏休みに車で出かけても大変な思いをしたことはない。大きな理由の一つとしてはドイツの各州それぞれが違った期間、学校の休みになっているからだと思う。来年に関して言えばたとえば、夏休みは、私の住んでいたNordrhein-Westfalen州は、7月9日から、8月21日まで、そして南のBayern州は、8月1日から、9月12日までとなる。それぞれの州で、イースター休み、夏休み、秋休み、冬休みの期間が違っている。よく考えられていると思う。
そして、とにかくうれしいことは凸凹がなく道がとてもよく整備され、アウトバーンがすばらしいのだ。制限速度がないのだから、時速200キロぐらい出している車も目にする。
ドイツからオランダ、フランス、オーストリアなどに車で移動するとすぐに制限速度の標識が出てくるし、道が悪くなるのが体感できる。
更にうれしいことは、ドイツには料金所がなく通行料を支払わなくてもよいことだ。
ドイツ国内の車の旅がなつかしい!!
タグ :ドイツの車事情
2011年11月27日
ドイツの誕生日は日本と違う?
我が家には誕生月が11月の者が2人いるのだが、「誕生日」ということで日本とドイツでは大きな違いがある。
それは職場で働いている場合は、自分の誕生日には、自分でケーキや、マフィン、クッキーなど焼いて職場の同僚に持っていくということだ。誕生日だというのに、朝から準備で忙しい。日本の感覚だと誕生日には、ケーキはもらうほうだが、ドイツではなんと自分で用意していくのだから。
確かにお誕生日を迎えるにあたって、日ごろの感謝の意を表すことはとても大切だと思うのだが。
更に日本と違う点は、お誕生日のお祝いはその当日かそれ以降に行い、誕生日前にはお祝いしないという点だ。11年前にドイツに行った年にはそのことを知らず、子供の誕生日会を誕生日の2週間ほど前にしてしまった。
理由をドイツ人に聞いたのだが、いまだにその理由がはっきりしない。
ところ変わればやり方も違う。異文化を知る楽しさはこんな身近なところにあると思う。
それは職場で働いている場合は、自分の誕生日には、自分でケーキや、マフィン、クッキーなど焼いて職場の同僚に持っていくということだ。誕生日だというのに、朝から準備で忙しい。日本の感覚だと誕生日には、ケーキはもらうほうだが、ドイツではなんと自分で用意していくのだから。
確かにお誕生日を迎えるにあたって、日ごろの感謝の意を表すことはとても大切だと思うのだが。
更に日本と違う点は、お誕生日のお祝いはその当日かそれ以降に行い、誕生日前にはお祝いしないという点だ。11年前にドイツに行った年にはそのことを知らず、子供の誕生日会を誕生日の2週間ほど前にしてしまった。
理由をドイツ人に聞いたのだが、いまだにその理由がはっきりしない。
ところ変わればやり方も違う。異文化を知る楽しさはこんな身近なところにあると思う。
タグ :ドイツの誕生日
2011年11月24日
今年は来ない愛犬ブラッキーへのX'mas招待?
今頃の時期になるとドイツではいつも我が家の愛犬ブラッキー宛てにサンタさんから(?)クリスマスパーティの招待状が届いていたが、残念ながら今年は来ない。
この招待状は実はブラッキーの通っていた犬の学校から送られてくるものだ。パーティは毎年12月中旬ごろの日曜日に開催される。
その日は、飼い主につれられた犬たちが、ライン川の近くのカフェハウスの前に集まるが、毎年80匹近く来ていたかな。まずは、皆でサンタさんが草の上をそりで犬にひかれてくるのを出迎え、それから飼い主たちと犬と一緒に全員、ライン川まで散歩。そこで犬たちはリードを外され、自由にライン河畔のフィールドを走り回る。とにかく寒いので私たち飼い主は早く暖かな珈琲でも飲みたいのだが、犬たちは、皆元気で遊びまわる。1時間ほどしてからまた、みなで歩いてカフェハウスへ。
そしていよいよサンタさんからのプレゼントをもらうのだが、1匹ずつちゃんと名前を呼ばれサンタさんからたくさんのかわいい形のビスケットの入った袋をもらう。食べ物に目がないブラッキーは目が飛び出しそうに嬉しそうだった!!
そのカフェは屋外のオープンテラスで、各テーブルには、ミカンやチョコレート、クリスマスのクッキーなどが用意されている。また、温かいスープやソーセージ、パン、コーヒーなども買うことができる。更に素晴らしいのは、ライブバンドも入り音楽も楽しめる。愛犬たちを横に座らせ、飼い主たちも話に花が咲く。本当に楽しいひと時だ。
犬たちのおかげで人間も素敵なクリスマスを過ごすことができて犬たちに感謝!!
こんなクリスマスパーティが日本にもあったらいいな。
この招待状は実はブラッキーの通っていた犬の学校から送られてくるものだ。パーティは毎年12月中旬ごろの日曜日に開催される。
その日は、飼い主につれられた犬たちが、ライン川の近くのカフェハウスの前に集まるが、毎年80匹近く来ていたかな。まずは、皆でサンタさんが草の上をそりで犬にひかれてくるのを出迎え、それから飼い主たちと犬と一緒に全員、ライン川まで散歩。そこで犬たちはリードを外され、自由にライン河畔のフィールドを走り回る。とにかく寒いので私たち飼い主は早く暖かな珈琲でも飲みたいのだが、犬たちは、皆元気で遊びまわる。1時間ほどしてからまた、みなで歩いてカフェハウスへ。
そしていよいよサンタさんからのプレゼントをもらうのだが、1匹ずつちゃんと名前を呼ばれサンタさんからたくさんのかわいい形のビスケットの入った袋をもらう。食べ物に目がないブラッキーは目が飛び出しそうに嬉しそうだった!!
そのカフェは屋外のオープンテラスで、各テーブルには、ミカンやチョコレート、クリスマスのクッキーなどが用意されている。また、温かいスープやソーセージ、パン、コーヒーなども買うことができる。更に素晴らしいのは、ライブバンドも入り音楽も楽しめる。愛犬たちを横に座らせ、飼い主たちも話に花が咲く。本当に楽しいひと時だ。
犬たちのおかげで人間も素敵なクリスマスを過ごすことができて犬たちに感謝!!
こんなクリスマスパーティが日本にもあったらいいな。
2011年11月24日
日本は鉛筆、ドイツは万年筆でスタート!!
日本では小学校に上がるとひらがなを習うが文字を書くには、鉛筆を使う。11年前にドイツに行ったときには、子供たちのために、書きやすい2Bなどの書きかた鉛筆を大量に買い求め、日本から持って行った。
ところがドイツでは、小学校で、アルファベットを書くときにすぐに木製の万年筆を使わされる。これには驚いた。そして、一度試してみたら、まるで羽ペンのような書き心地で、ながれるようにスムーズにかけるのに、またまたびっくり。
また、万年筆だから、間違えたらどうするのかと心配していたら、ちゃんときれいに消せる鉛筆のような形の消しゴムがあるのだ。ただ基本的には、間違えは消しゴムで消さず、線を引き、その下に新たに書くように指導を受ける。
よい点は、間違えが消えずに残り、どこを間違えたのかが分かり、次に参考にできることだ。もちろん万年筆はすべての教科に使うので、算数の計算や問題を解くときに非常によい。間違えたところが一目瞭然で次回にいかせるのだから。
このように間違えを書面に残すことの意義をドイツの学校から学んだ。ただ、小学生のころから、間違えをきれいに消しゴムで消すことに慣れている私には、どうも見た目がきれいでないドイツ式には、戸惑いもあるのだが。
ところがドイツでは、小学校で、アルファベットを書くときにすぐに木製の万年筆を使わされる。これには驚いた。そして、一度試してみたら、まるで羽ペンのような書き心地で、ながれるようにスムーズにかけるのに、またまたびっくり。
また、万年筆だから、間違えたらどうするのかと心配していたら、ちゃんときれいに消せる鉛筆のような形の消しゴムがあるのだ。ただ基本的には、間違えは消しゴムで消さず、線を引き、その下に新たに書くように指導を受ける。
よい点は、間違えが消えずに残り、どこを間違えたのかが分かり、次に参考にできることだ。もちろん万年筆はすべての教科に使うので、算数の計算や問題を解くときに非常によい。間違えたところが一目瞭然で次回にいかせるのだから。
このように間違えを書面に残すことの意義をドイツの学校から学んだ。ただ、小学生のころから、間違えをきれいに消しゴムで消すことに慣れている私には、どうも見た目がきれいでないドイツ式には、戸惑いもあるのだが。
タグ :ドイツの小学教育
2011年11月23日
ドイツは鍵の世界!!!
ドイツに行っていつも思うことは「鍵の世界」ということだ。11年前にドイツで生活をスタートした矢先にドアを開けたままポストに郵便物を取りに行ったとき、風が強くてドアが閉まってしまい、締め出されてしまった。ドイツのドアは自動ロックのものが多い。その時はドイツ語も分からず、階上に住む大家さんに頼み、開けてもらった。そして2回目の失敗は、鍵を玄関に置いたままでドアを閉めてしまい、締め出されてしまった!!!この時は鍵屋さんを読んで、100ユーロを払って開けてもらった。
これは各家のドアーの鍵の話だが、何家族もが同じ建物内に住んでいる場合は、共通のドアを開けるにもまた別の鍵がいる。このドアも自動に閉まってしまうから大変だ。
また、地下に洗濯機が置いてあるのだが、ここに行くにも鍵がいる。更には家の中の各部屋にもすべて鍵があり、ロックできるようになっている。つまりトイレやバスルーム以外にも子供部屋、書斎、そして寝室にも。
日本の家は、ふすまだったり、個室でも各部屋に鍵がない場合が多いと思うのがだ、ドイツではやはり家族といえども「個」ということでプライバシーを大切にするからかな。
ドイツに行くと途端に鍵の数が増える!!鍵の管理は頭が痛い!!
これは各家のドアーの鍵の話だが、何家族もが同じ建物内に住んでいる場合は、共通のドアを開けるにもまた別の鍵がいる。このドアも自動に閉まってしまうから大変だ。
また、地下に洗濯機が置いてあるのだが、ここに行くにも鍵がいる。更には家の中の各部屋にもすべて鍵があり、ロックできるようになっている。つまりトイレやバスルーム以外にも子供部屋、書斎、そして寝室にも。
日本の家は、ふすまだったり、個室でも各部屋に鍵がない場合が多いと思うのがだ、ドイツではやはり家族といえども「個」ということでプライバシーを大切にするからかな。
ドイツに行くと途端に鍵の数が増える!!鍵の管理は頭が痛い!!
タグ :ドイツの鍵
2011年11月21日
「期間限定」、「季節限定」の多い日本商品!!
10年ぶりに日本に帰ってよく目にするのが期間限定や季節限定商品だ。ケーキや和菓子、カフェなどいろいろなところでみかける。
マロンのお茶、モンブランケーキ、カボチャのプリン。
要は「旬」のものを使った食べ物になるのかな。中には、季節にあまり関係ないようなものもあるが。
ドイツにももちろん「旬」の果物や野菜などたくさんあるが、「期間限定」というような言い方はしない。
日本にいるとなんだかこの言葉に惑わされて「限定」食品を食べたり、買ったりしてしまう。これも商法のひとつなのだろうが。
「旬」という言葉を聞いた方が食欲をそそられ、美味しくいただけるような気がするのは私だけかな。
マロンのお茶、モンブランケーキ、カボチャのプリン。
要は「旬」のものを使った食べ物になるのかな。中には、季節にあまり関係ないようなものもあるが。
ドイツにももちろん「旬」の果物や野菜などたくさんあるが、「期間限定」というような言い方はしない。
日本にいるとなんだかこの言葉に惑わされて「限定」食品を食べたり、買ったりしてしまう。これも商法のひとつなのだろうが。
「旬」という言葉を聞いた方が食欲をそそられ、美味しくいただけるような気がするのは私だけかな。
2011年11月18日
ドイツで感じた「ろうそく」の不思議な力。
ドイツにいる時、寒い季節に、家ではきれいなガラスの入れ物に平たい小さなろうそくをともし、いつもテーブルの上に置いていた。
ろうそくは日本ではお仏壇に灯すというイメージが強いかもしれないが、ドイツではレストランやカフェをはじめ、美容室、パン屋さん、お店、あるゆるところに置かれている。もちろん家の中でも灯していることも多い。
ドイツの冬は長くで寒い。そんな寒い寒い冬の夜、家路に急いでいるとき、暗い中に家の窓に赤々と燃えているろうそくのあかりを何度も目にした。そんな光景をみると途端に心も体も暖まる気がした。そしていつも「マッチ売りの少女」の話を思い出していた。ろうそくのあかりは人に力を与えてくれる不思議な魔法のようなものだ。
今、家で赤い小さなガラスの入れ物にドイツから持ってきた小さなろうそくを入れてともしている。ゆらゆらゆれているろうそくのあかりを見ていると気持ちがとても落ちつく。暖かな気持ちになる。
明るすぎる部屋よりは少し薄暗い方が、ろうそくにあう。
日本でろうそくを眺めながら、あの寒いドイツの真っ暗な夜に身も心も暖めてくれたろうそくのあかりを思う。
ろうそくは日本ではお仏壇に灯すというイメージが強いかもしれないが、ドイツではレストランやカフェをはじめ、美容室、パン屋さん、お店、あるゆるところに置かれている。もちろん家の中でも灯していることも多い。
ドイツの冬は長くで寒い。そんな寒い寒い冬の夜、家路に急いでいるとき、暗い中に家の窓に赤々と燃えているろうそくのあかりを何度も目にした。そんな光景をみると途端に心も体も暖まる気がした。そしていつも「マッチ売りの少女」の話を思い出していた。ろうそくのあかりは人に力を与えてくれる不思議な魔法のようなものだ。
今、家で赤い小さなガラスの入れ物にドイツから持ってきた小さなろうそくを入れてともしている。ゆらゆらゆれているろうそくのあかりを見ていると気持ちがとても落ちつく。暖かな気持ちになる。
明るすぎる部屋よりは少し薄暗い方が、ろうそくにあう。
日本でろうそくを眺めながら、あの寒いドイツの真っ暗な夜に身も心も暖めてくれたろうそくのあかりを思う。
2011年11月18日
靴を大切に考えるドイツの人たち!!
最近日本でも健康靴としてドイツ製の靴をよく紹介しているのを目にする。
ドイツの靴は、本当にしっかりとよくできていると思う。日本のようにファッション性よりも実質性が重視されている気がする。ドイツにいる間、私が履くような小さなサイズの靴は種類が少なくてさがすのが大変だったが、それにもましておしゃれな靴がなかなか見つからなかった。(小さめのサイズやおしゃれな靴を探しに、パリやイタリアに行く日本の人もいた。)
そしてもっと驚いたのは、ドイツでは靴の値段が物価の割に高いことだ。
値段が高い靴だが、これは小さな子供たちの靴も同じことがいえ、ちょっとした靴でも60-70ユーロほどする。日本的感覚だと小さい子はすぐに足が大きくなるので、あまり高い靴を買うのは躊躇してしまうが、ドイツの人は「靴」は体を支える大切のものと考えているので、高い靴を買うこともいとわない。しっかりしたものを子供にも選ぶようだ。そして日本の子ども靴によく見るマジックテープ式のものよりひもできちんと結ぶ形のものが多い。
足は、人間の体、健康の基本と考えるのがドイツの人のようだ。特に成長期の子供たちには、しっかりした靴を選ぶ親が多い。
私も初めは、「子供の靴にこんなにお金をかけるなんて!」と思っていたが、実際に子供用の安い靴はなかなか見つからないし、靴の大切さを認識するようになり、毎年のように買いかえていた。
日本でも「シューマイスター」のような靴専門の人がいる靴屋さんも出てきているが、まだまだファッション性の方が重視されているような気がする。私自身も歩きやすいしっかりした靴を日頃は履いて、TPOに応じて履き替えるようにしている。やはりかかとの高い靴は疲れる!!膝が前に出てしまい、姿勢も悪くなってしまう。
胸を張り、堂々と歩くドイツの人々は自分に合った靴をしっかり選んでいるのだろう!!
ドイツの靴は、本当にしっかりとよくできていると思う。日本のようにファッション性よりも実質性が重視されている気がする。ドイツにいる間、私が履くような小さなサイズの靴は種類が少なくてさがすのが大変だったが、それにもましておしゃれな靴がなかなか見つからなかった。(小さめのサイズやおしゃれな靴を探しに、パリやイタリアに行く日本の人もいた。)
そしてもっと驚いたのは、ドイツでは靴の値段が物価の割に高いことだ。
値段が高い靴だが、これは小さな子供たちの靴も同じことがいえ、ちょっとした靴でも60-70ユーロほどする。日本的感覚だと小さい子はすぐに足が大きくなるので、あまり高い靴を買うのは躊躇してしまうが、ドイツの人は「靴」は体を支える大切のものと考えているので、高い靴を買うこともいとわない。しっかりしたものを子供にも選ぶようだ。そして日本の子ども靴によく見るマジックテープ式のものよりひもできちんと結ぶ形のものが多い。
足は、人間の体、健康の基本と考えるのがドイツの人のようだ。特に成長期の子供たちには、しっかりした靴を選ぶ親が多い。
私も初めは、「子供の靴にこんなにお金をかけるなんて!」と思っていたが、実際に子供用の安い靴はなかなか見つからないし、靴の大切さを認識するようになり、毎年のように買いかえていた。
日本でも「シューマイスター」のような靴専門の人がいる靴屋さんも出てきているが、まだまだファッション性の方が重視されているような気がする。私自身も歩きやすいしっかりした靴を日頃は履いて、TPOに応じて履き替えるようにしている。やはりかかとの高い靴は疲れる!!膝が前に出てしまい、姿勢も悪くなってしまう。
胸を張り、堂々と歩くドイツの人々は自分に合った靴をしっかり選んでいるのだろう!!
タグ :ドイツの靴
2011年11月16日
犬にもある食欲の秋?
我が家の愛犬ブラッキーのここ数日の食欲はただならぬものがある。
まずは昨日、私がいない間に、カバンの中にいれて置いた友達に渡すお菓子の箱を食いちぎり、中身を食べてしまっていた。
そして今日は、旅行用ポーチの中の歯磨き粉とローションがブラッキーの寝床に散乱!!歯磨き粉にはしっかり歯型が。
更にかわいいイチゴのデコレーションの形をした携帯用ストラップの飾りにもブラッキーの噛んだあとがあった。
ブラッキー用のお菓子もケージの上の箱にいれているのだが、ジャンプしてその袋を取り、中身を全部食べ、乾燥剤にも歯型。
もちろんさすがに乾燥剤は食べていなかったが・・・・
もともと食べ物に目がないブラッキーだが、ここまですごいと唖然とする。犬は飼い主に似るというが・・・・
何だが犬も人間のように「食欲の秋」がある気がしてきた今日この頃である。
まずは昨日、私がいない間に、カバンの中にいれて置いた友達に渡すお菓子の箱を食いちぎり、中身を食べてしまっていた。
そして今日は、旅行用ポーチの中の歯磨き粉とローションがブラッキーの寝床に散乱!!歯磨き粉にはしっかり歯型が。
更にかわいいイチゴのデコレーションの形をした携帯用ストラップの飾りにもブラッキーの噛んだあとがあった。
ブラッキー用のお菓子もケージの上の箱にいれているのだが、ジャンプしてその袋を取り、中身を全部食べ、乾燥剤にも歯型。
もちろんさすがに乾燥剤は食べていなかったが・・・・
もともと食べ物に目がないブラッキーだが、ここまですごいと唖然とする。犬は飼い主に似るというが・・・・
何だが犬も人間のように「食欲の秋」がある気がしてきた今日この頃である。
タグ :食欲の秋
2011年11月15日
左利きは右利きになおす?
今日の朝刊にスイスの高級時計の宣伝として母親と女の子の写真が大きくのっていた。その中で、目を引いたのは女の子が「左利き」ということだ。今の日本では「左利き」を「右利き」になおすという風潮があるのかはわからないが、少なくとも私の子供のころは、親が「左利き」の子供は「右利き」になるようになおしていた。
ドイツにいる間も友達で「左利き」の人も多かったのだが、特に親に「右利き」になおすように言われたことはなかったそうだ。
そういえば、アメリカの大学に通った時も一人一人座る椅子になっていたのだが、左利きの人用に座りやすくまた、ノートをとりやすいようにできている椅子もあった。
ドイツでもアメリカでも左利きの人が日常生活において不便を感じないようにいろいろ考えられているようだ。
私自身「右利き」なのでよくわからないのだが、日本では「左利き」だと不便なことがあるのかな?
「左利き」の女の子が載っている写真を見てそんなことを考えた。
ドイツにいる間も友達で「左利き」の人も多かったのだが、特に親に「右利き」になおすように言われたことはなかったそうだ。
そういえば、アメリカの大学に通った時も一人一人座る椅子になっていたのだが、左利きの人用に座りやすくまた、ノートをとりやすいようにできている椅子もあった。
ドイツでもアメリカでも左利きの人が日常生活において不便を感じないようにいろいろ考えられているようだ。
私自身「右利き」なのでよくわからないのだが、日本では「左利き」だと不便なことがあるのかな?
「左利き」の女の子が載っている写真を見てそんなことを考えた。
タグ :左利き
2011年11月15日
noisy colors and quiet colors?
英語の形容詞は、本当に面白い!!
とにかくいろいろな意味を持っている。日本語でも一つの形容詞にいろいろな意味があるが、英語は形容詞をテーマに何冊もの本が書けるくらい奥が深い。
たとえば「派手な色」という時に、"noisy colors"という。それに対して地味な色は”quiet colors"
知らないとなかなか出てこない。
それでは"tall orders"とはなんだろう?
これは無理な注文という意味になる。
"a tall tale"は「作り話」
"a hard head”は「石頭」
何だか日本語のニュアンスに近いものもある。
英語の形容詞を辞書で見てみるととても楽しいし発見がある。
秋の夜長、是非辞書を引き、英語を楽しもう!!
とにかくいろいろな意味を持っている。日本語でも一つの形容詞にいろいろな意味があるが、英語は形容詞をテーマに何冊もの本が書けるくらい奥が深い。
たとえば「派手な色」という時に、"noisy colors"という。それに対して地味な色は”quiet colors"
知らないとなかなか出てこない。
それでは"tall orders"とはなんだろう?
これは無理な注文という意味になる。
"a tall tale"は「作り話」
"a hard head”は「石頭」
何だか日本語のニュアンスに近いものもある。
英語の形容詞を辞書で見てみるととても楽しいし発見がある。
秋の夜長、是非辞書を引き、英語を楽しもう!!
タグ :英語の形容詞
2011年11月14日
「インモータルズ」って何?
今「インモータルズ」という映画をやっているが、英語のタイトルは、"The Immortals"つまり、古代ギリシア・ローマ神話の神々のことだ。英語をカタカナで表記することは不可能だが、少なくとも英語の発音に近い「イモータルズ」にしてほしかった。
もし今、意味が分からくてもあとでこの単語"immortal"を習ったとき、以前見た映画のタイトルだったなと思いだせば、親しみもわき単語も覚えやすい。
もし英語のオリジナルタイトルを日本語のカタカナでそのまま表す時は、是非英語にできるだけ忠実に変えてほしい。それだけでも英語の単語量は増えていく。
先日ラジオを聞いているときまた同じことを思った。アナウンサーがしきりに「フアン」という言葉を何度もいうのだが、つまり英語の"fan"のことだ。この言葉もできたら、「ファン」と言ってほしい。もちろん英語の発音とは違うが少しでも近くなる。
日本にはたくさんの和製英語が氾濫しているが、日本語と英語の意味の違いがない言葉に関しては、英語の発音に近いカタカナ表記であれば、英語学習にかなり役立つと思うのだが。
もし今、意味が分からくてもあとでこの単語"immortal"を習ったとき、以前見た映画のタイトルだったなと思いだせば、親しみもわき単語も覚えやすい。
もし英語のオリジナルタイトルを日本語のカタカナでそのまま表す時は、是非英語にできるだけ忠実に変えてほしい。それだけでも英語の単語量は増えていく。
先日ラジオを聞いているときまた同じことを思った。アナウンサーがしきりに「フアン」という言葉を何度もいうのだが、つまり英語の"fan"のことだ。この言葉もできたら、「ファン」と言ってほしい。もちろん英語の発音とは違うが少しでも近くなる。
日本にはたくさんの和製英語が氾濫しているが、日本語と英語の意味の違いがない言葉に関しては、英語の発音に近いカタカナ表記であれば、英語学習にかなり役立つと思うのだが。
タグ :和製英語
2011年11月12日
第3回Cafe &Talk開催―英語の質問なんでもどうぞ!!
クロスカルチャーネットワーク主催第3回"Cafe&Talk"開催。
明るい雰囲気のカフェで珈琲を飲みながら、土曜日の朝、楽しく英語の勉強をする。
日時:2011年12月3日(土)
場所:武蔵野プレイス (武蔵境駅南口徒歩1分)
1F cafe 「フェルマータ」
時間:10:00 ~ 11:30
内容:1.英語のあらゆる質問に答える(なんでもどうぞ)
2.各自自分の用意してきたもの(2パラグラフほどの短めのエッセイ、コメントなんでもOK)を発表
添削したりコメントを加えます。
3.日本事象を取り上げて英語で説明。(今回は「お中元」「お歳暮」などを予定)
定員:7名(残席あと3名)
会費:1,500円
講師:Yuko Miura
お問い合わせ及び申し込みは、メールにてどうぞ。
yukomiura05@yahoo.co.jp
クロスカルチャーネットワーク
明るい雰囲気のカフェで珈琲を飲みながら、土曜日の朝、楽しく英語の勉強をする。
日時:2011年12月3日(土)
場所:武蔵野プレイス (武蔵境駅南口徒歩1分)
1F cafe 「フェルマータ」
時間:10:00 ~ 11:30
内容:1.英語のあらゆる質問に答える(なんでもどうぞ)
2.各自自分の用意してきたもの(2パラグラフほどの短めのエッセイ、コメントなんでもOK)を発表
添削したりコメントを加えます。
3.日本事象を取り上げて英語で説明。(今回は「お中元」「お歳暮」などを予定)
定員:7名(残席あと3名)
会費:1,500円
講師:Yuko Miura
お問い合わせ及び申し込みは、メールにてどうぞ。
yukomiura05@yahoo.co.jp
クロスカルチャーネットワーク
2011年11月11日
音読の勧め!!
今、塾で中学生に英語を教えているが、教科書の音読が教室であまりされていないことを聞いて唖然!
私が中学生の時は、テープを聞いてその後リピートする以外に、先生が発音、イントネーションやリズムの指導をしながら、何度も発音してくださり、後について練習した。
今は、外国人による授業もあるようだが、肝心の教科書の音読が置き去りにされているような気がする。
英語には、発音、リズム、イントネーションの習得が不可欠だ。特に日本語と違うリズムがある。これも早いうちに何度も繰り返せば、体に身に付く。ぜひもっと力を入れてほしい。
自分の子供がドイツで日本人学校に行っていた時、国語の先生が音読の大切さをいつもおっしゃっていた。
海外に住み日本語に接することが少なかったが、この音読のおかげで今でも日本語が大好きだ。
少なくとも授業で正しい英語を聞き、英語の特有のリズム、音を体感してほしい。
私が中学生の時は、テープを聞いてその後リピートする以外に、先生が発音、イントネーションやリズムの指導をしながら、何度も発音してくださり、後について練習した。
今は、外国人による授業もあるようだが、肝心の教科書の音読が置き去りにされているような気がする。
英語には、発音、リズム、イントネーションの習得が不可欠だ。特に日本語と違うリズムがある。これも早いうちに何度も繰り返せば、体に身に付く。ぜひもっと力を入れてほしい。
自分の子供がドイツで日本人学校に行っていた時、国語の先生が音読の大切さをいつもおっしゃっていた。
海外に住み日本語に接することが少なかったが、この音読のおかげで今でも日本語が大好きだ。
少なくとも授業で正しい英語を聞き、英語の特有のリズム、音を体感してほしい。
2011年11月10日
スローテンポの大切さ
きのうのjazz vocalのレッスンで"Autumn leaves"(枯葉)を歌ったのだが、2 ビートのゆっくりしたテンポで歌ってみた。こんなにゆっくり歌うのは私にとって初めて。歌い終わったときに、いつもよりゆったりと自分の気持ちを込めて納得のいくように歌えた気がした。そしてスローテンポの大切さをおもわず実感した。
これは生活の中でもいえると思う。時間のゆとりは心のゆとりにもつながる。今日、久しぶりに時間があったので、愛犬ブラッキーとゆっくりと散歩をすることができた。近くの公園のベンチにコーヒーを飲みながら座り、たくさんの実のなった柿の木や、色ずく木々の葉を眺めたり、鳥のさえずりを聞いたり・・・・ゆったりした気持ちになれた。ブラッキーもベンチの前に座り、目を細め、美しい景色を見て自然の中で癒されているようだった。私もなぜだか、ブラッキーにやさしくなり「お利口さんね~!」の連発。
いつもせわしなく生活しているが、やはりのんびりすることは大切だと痛感した。これは歌でも生活でもみな共通しているように思う。”slow food "という言葉が一時はやったが、ゆったりとした気分で過ごすことはとても大きな意味があるような気がする。
これは生活の中でもいえると思う。時間のゆとりは心のゆとりにもつながる。今日、久しぶりに時間があったので、愛犬ブラッキーとゆっくりと散歩をすることができた。近くの公園のベンチにコーヒーを飲みながら座り、たくさんの実のなった柿の木や、色ずく木々の葉を眺めたり、鳥のさえずりを聞いたり・・・・ゆったりした気持ちになれた。ブラッキーもベンチの前に座り、目を細め、美しい景色を見て自然の中で癒されているようだった。私もなぜだか、ブラッキーにやさしくなり「お利口さんね~!」の連発。
いつもせわしなく生活しているが、やはりのんびりすることは大切だと痛感した。これは歌でも生活でもみな共通しているように思う。”slow food "という言葉が一時はやったが、ゆったりとした気分で過ごすことはとても大きな意味があるような気がする。
タグ :ジャズヴォーカル
Posted by ゆっこ at
00:52
│Comments(0)
2011年11月09日
目まぐるしく動く眉と目?
今日街で今にも泣きそうな顔の5歳ぐらいの男の子を見かけた。その顔の表情があまりにもリアル!!でこちらにかなり大きなインパクトを与えた。
こんなに豊かな?顔の表情を見たのは久しぶり。
日本に帰ってから感じることは「顔の表情の乏しさ」だ。話していても表情に変化がなく気が抜けてしまうこともある。その点小さな子供たちは、私たち大人に比べて表情が豊かだと思う。色々な表情で気持ちを伝える。
始めて米国人と話したときあまりに目やまゆ毛、おでこ?がめまぐるしく動くのでびっくりしたことがある。ドイツの人はどちらかというと米国人ほと表情の変化はないが、少なくとも目元や口元はよく動く。
とにかく顔の表情の動きをみているだけで楽しくなる。コミュニケーションも楽しくなる。
日本に帰り、表情変化の乏しくなりつつある私も外国人の友達と話すときは、つられて目がくるくる動いたり、眉毛がいそがしく上下しているのかな?
こんなに豊かな?顔の表情を見たのは久しぶり。
日本に帰ってから感じることは「顔の表情の乏しさ」だ。話していても表情に変化がなく気が抜けてしまうこともある。その点小さな子供たちは、私たち大人に比べて表情が豊かだと思う。色々な表情で気持ちを伝える。
始めて米国人と話したときあまりに目やまゆ毛、おでこ?がめまぐるしく動くのでびっくりしたことがある。ドイツの人はどちらかというと米国人ほと表情の変化はないが、少なくとも目元や口元はよく動く。
とにかく顔の表情の動きをみているだけで楽しくなる。コミュニケーションも楽しくなる。
日本に帰り、表情変化の乏しくなりつつある私も外国人の友達と話すときは、つられて目がくるくる動いたり、眉毛がいそがしく上下しているのかな?
タグ :顔の表情
2011年11月07日
何でもありの日本!!
ドイツの今頃は11月10日のマルチン祭が終わると、街はクリスマスカラーに染まっていく。クリスマスマルクト(市場)の準備は11月中旬ぐらいから始まり、小さなお店が並び始める。
11月下旬にはもうマルクトがオープンし12月23日の午前中まで毎日開いている。焼き栗の匂いや、シナモンや香辛料の沢山入ったグリューワイン、様々な種類のソーセージ、いい匂いが街角からしてくる。そしてクリスマスのモミの木のマルクトもいたるところでオープンする。
クリスマスのリースや、飾り、イリュミネーションも美しい。
対する日本は、11月の今の時期はいろいろなものを目にする。
クリスマスの飾り、クリスマスケーキの案内、お正月の飾り、おせち料理、年賀状の案内、お歳暮、一度にたくさんのものが目に入り、
目移りしてしまう。
見方を変えれば、何でもありで楽しいのだが、もう少し落ち着いて11月から、年末を過ごしたいと思う。
それでなくても年の瀬はわさわさするので、ドイツのように「クリスマス」カラー、一色なのは有難い。厳かな落ち着いた気持ちで年の瀬と新年を迎えることができる。
なんだか途端に、せわしくなったきた!!!
11月下旬にはもうマルクトがオープンし12月23日の午前中まで毎日開いている。焼き栗の匂いや、シナモンや香辛料の沢山入ったグリューワイン、様々な種類のソーセージ、いい匂いが街角からしてくる。そしてクリスマスのモミの木のマルクトもいたるところでオープンする。
クリスマスのリースや、飾り、イリュミネーションも美しい。
対する日本は、11月の今の時期はいろいろなものを目にする。
クリスマスの飾り、クリスマスケーキの案内、お正月の飾り、おせち料理、年賀状の案内、お歳暮、一度にたくさんのものが目に入り、
目移りしてしまう。
見方を変えれば、何でもありで楽しいのだが、もう少し落ち着いて11月から、年末を過ごしたいと思う。
それでなくても年の瀬はわさわさするので、ドイツのように「クリスマス」カラー、一色なのは有難い。厳かな落ち着いた気持ちで年の瀬と新年を迎えることができる。
なんだか途端に、せわしくなったきた!!!