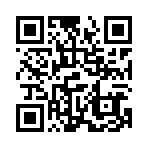2012年06月29日
グローバル社会に生きるとは?
今日は私が社会人メンターをしている大学での特別シンポジウム「グローバル人材を育てる~女性の新しいチャレンジ」に参加した。
パネリストはグローバルなビジネス界で活躍している方3名で、「グローバルビジネス女性の条件」などをテーマにいろいろなトークがあった。どのパネリストもdiversity(多様性)とinclusiveness(受容性)の大切さを強調なさっていた。つまり、さまざまな言葉・文化・倫理観・価値観を持った人々に触れ、自分との違いを認識する。自分を同化させるのではなく、日本人としてのidentityをもち、違いを違いとして認め、自分はどうなのかを考えることが大切。
同感である。ただこの「日本人としてのidentity」が難しく、人によって異なる場合もあると思う。今日の話の中にあった「わび」「さび」などは日本人特有の文化の一つだと思うが、identityはかなりあいまいなものであるような気がする。あまりこの「日本人のidentity」にとらわれてしまうと自由な発想が生まれないのではないだろうか?個性が育たない気がする。
大事なことはその違いや違った発想に対して「自分がどう感じるか」ということではないだろうか?新しい発想や価値観を自分の考えと照らし合わせる。そして自分の気持ちに正直に向き合って考える。そのプロセスがとても大事だと思う。私自身、「自分の意見をはっきり述べる」「建前より本音を重視する」ストレートな人間関係を好む。外国に行き、外国の友達と話していると、気持ちが開放され、本当の自分になれるような気がする。10代で初めて米国に行き初めて本当の自分に向き合えた気がした。
今日のパネルトークの中で何度も強調された「日本人としてのidentityを忘れないこと」にとらわれることなく、自分独自のidentity 、個性を作り上げていく生き方をこれからもしていきたい。
違いを楽しみながら、誰とも違う自分を築いていくプロセス、かなり魅力的だ!!違った個性との出会い、これこそグローバル社会の醍醐味だと考える。
パネリストはグローバルなビジネス界で活躍している方3名で、「グローバルビジネス女性の条件」などをテーマにいろいろなトークがあった。どのパネリストもdiversity(多様性)とinclusiveness(受容性)の大切さを強調なさっていた。つまり、さまざまな言葉・文化・倫理観・価値観を持った人々に触れ、自分との違いを認識する。自分を同化させるのではなく、日本人としてのidentityをもち、違いを違いとして認め、自分はどうなのかを考えることが大切。
同感である。ただこの「日本人としてのidentity」が難しく、人によって異なる場合もあると思う。今日の話の中にあった「わび」「さび」などは日本人特有の文化の一つだと思うが、identityはかなりあいまいなものであるような気がする。あまりこの「日本人のidentity」にとらわれてしまうと自由な発想が生まれないのではないだろうか?個性が育たない気がする。
大事なことはその違いや違った発想に対して「自分がどう感じるか」ということではないだろうか?新しい発想や価値観を自分の考えと照らし合わせる。そして自分の気持ちに正直に向き合って考える。そのプロセスがとても大事だと思う。私自身、「自分の意見をはっきり述べる」「建前より本音を重視する」ストレートな人間関係を好む。外国に行き、外国の友達と話していると、気持ちが開放され、本当の自分になれるような気がする。10代で初めて米国に行き初めて本当の自分に向き合えた気がした。
今日のパネルトークの中で何度も強調された「日本人としてのidentityを忘れないこと」にとらわれることなく、自分独自のidentity 、個性を作り上げていく生き方をこれからもしていきたい。
違いを楽しみながら、誰とも違う自分を築いていくプロセス、かなり魅力的だ!!違った個性との出会い、これこそグローバル社会の醍醐味だと考える。
Posted by ゆっこ at
00:57
│Comments(0)
2012年06月28日
ドイツと日本では違う筋肉運動???
ドイツから日本に帰国して感じることは、日常生活で使われる筋肉が違うということだ。ドイツではいつも「背伸び」をして暮らしていた気がする。つまりすべてのものが高い位置にあるので背伸びしないと届かない。昨日、近くのスポーツジムに行ったのだが、更衣室のロッカールームの開きにある鏡を見るのに、膝を曲げていることに気がついた。ドイツでは、背伸びをして見ていたのに。また、ドイツのジムにはフリードリンクサービスがあったのだが、棚のカフェのカップを取るのにも手が届かない。いつも周りにいるドイツ人に頼んでいた。
ドイツにいたときはバーカウンターの椅子に座るのも高くて大変。やっと座っても足がつかない!!
ドイツ人は本当に背が高い。いつも「ガリバー旅行記」を思い出し、自分の背が急に小さくなってしまったような錯覚に陥った。
台所の流し台の位置も高く食器戸棚も高いところにあり、背伸びをして食器を取っていた。
そして日本に帰り、狭いところを通り抜けるために腰をかがめたり、混雑しているところでは体の向きを変えたり…さらには満員電車の中では思いカバンを持ち上げて、スペースを作ったり。体の違う部分の筋肉が使われているような気がする。
住む場所により、筋肉運動が違うことを発見した!!!日本ではあまりしない「背伸び運動」も心がけてするようにしよう!!
ドイツにいたときはバーカウンターの椅子に座るのも高くて大変。やっと座っても足がつかない!!
ドイツ人は本当に背が高い。いつも「ガリバー旅行記」を思い出し、自分の背が急に小さくなってしまったような錯覚に陥った。
台所の流し台の位置も高く食器戸棚も高いところにあり、背伸びをして食器を取っていた。
そして日本に帰り、狭いところを通り抜けるために腰をかがめたり、混雑しているところでは体の向きを変えたり…さらには満員電車の中では思いカバンを持ち上げて、スペースを作ったり。体の違う部分の筋肉が使われているような気がする。
住む場所により、筋肉運動が違うことを発見した!!!日本ではあまりしない「背伸び運動」も心がけてするようにしよう!!
タグ :ドイツ
2012年06月26日
English compositionは必須!!
大学時代に交換留学で行った米国州立大学では,まずは"English composition"の授業を取らされた。米国人の学生たちも全員必ず大学ではこの授業をとるようになっている。これはいわゆる作文の授業で、文法や文のまとめ方、コロンやセミコロンの使い方などあらゆる内容を学ぶ。そしてこの授業でアメリカ人の学生たちがいかに文法ミスが多いかを知り驚いた。むしろ英語が母国語でない私の方が、文法はよくできた。つまり、言葉を話す能力と書く能力は一致しないことがある。日本人がいかに上手に日本語を話しても文章を書くとなるとまた話は違ってくる。いくら母国語とはいえ誤字や語法の間違いなどもあるだろう。文章のまとめ方がきちんとできていないこともある。
日本の大学では、このcompositionに相当する国語(日本語)の作文あるいや論文の授業は、必修になっていない。大学ではゼミのレポートや論文を書くという課題が多い。4年間の勉強の初めにまずはもう一度日本語の作文、論文の書き方の授業があってもよいと思う。大学においてきちんと書けることは必須条件だ。
米国大学で全員"composition"の授業が必須というやり方には賛成だ。
日本の大学では、このcompositionに相当する国語(日本語)の作文あるいや論文の授業は、必修になっていない。大学ではゼミのレポートや論文を書くという課題が多い。4年間の勉強の初めにまずはもう一度日本語の作文、論文の書き方の授業があってもよいと思う。大学においてきちんと書けることは必須条件だ。
米国大学で全員"composition"の授業が必須というやり方には賛成だ。
2012年06月24日
「ドイツを知る」は「日本を知る」
先日「ドイツ人の知りたい日本」というワークショップに参加した。講師はドイツに30年在住なさり、現地の大学で日本語を教えていらっしゃる先生。ドツ人にどのように日本の日常を説明していくのか。その背後にある文化の違いは?
「なぜ日本人は残業をするのか?」「なぜ日本人は大学で勉強したのとは違う分野の会社に就職するのか?」「なぜ、普段は控えめなのにカラオケではあんなに感情をこめて歌うのか?」など本当に様々な質問があり、それにグループで話し合い、答えていくというワークショップ。日本人の私たちも皆答えがいろいろ。
日本人でも年代、性別、育った環境により答えは、さまざま。また、答えるには、ドイツと日本の文化、社会の仕組みなどあるゆる要素が考慮されなければならない。
一つの決まった答えはない。
「ドイツ人の質問に答える」ことは日本をもう一度見つめなおすことにつながる。今回のワークショップはわたしにとって、むしろ「日本を知る」ワークショップだった。
そしてひとつ心に残った先生の言葉がある。それは、「なぜ日本の店員はあんなにお客さんに対して親切なのか?本当に心がこもっているのか?」という質問に対して参加者の多くが、「あれはマニュアルに従っているだけで本心からではない」と答えた。
そして先生は、「あれは本心からではありませんが、丁寧な応対をされてとても気持ちがいいです。嘘でもうれしい!!」とおっしゃった。
私も日本に帰国して、どうもあの心のこもっていないようなマニュアル通りの応対の仕方があまり好きでなかった。でも先生のようにポジティブに受け入れればいいんだと納得。これからは楽しんでみようとおもった。
違いを受け入れ、楽しむ。そんなしなやかな心をもった生き方を先生から学んだ1日だった。
「なぜ日本人は残業をするのか?」「なぜ日本人は大学で勉強したのとは違う分野の会社に就職するのか?」「なぜ、普段は控えめなのにカラオケではあんなに感情をこめて歌うのか?」など本当に様々な質問があり、それにグループで話し合い、答えていくというワークショップ。日本人の私たちも皆答えがいろいろ。
日本人でも年代、性別、育った環境により答えは、さまざま。また、答えるには、ドイツと日本の文化、社会の仕組みなどあるゆる要素が考慮されなければならない。
一つの決まった答えはない。
「ドイツ人の質問に答える」ことは日本をもう一度見つめなおすことにつながる。今回のワークショップはわたしにとって、むしろ「日本を知る」ワークショップだった。
そしてひとつ心に残った先生の言葉がある。それは、「なぜ日本の店員はあんなにお客さんに対して親切なのか?本当に心がこもっているのか?」という質問に対して参加者の多くが、「あれはマニュアルに従っているだけで本心からではない」と答えた。
そして先生は、「あれは本心からではありませんが、丁寧な応対をされてとても気持ちがいいです。嘘でもうれしい!!」とおっしゃった。
私も日本に帰国して、どうもあの心のこもっていないようなマニュアル通りの応対の仕方があまり好きでなかった。でも先生のようにポジティブに受け入れればいいんだと納得。これからは楽しんでみようとおもった。
違いを受け入れ、楽しむ。そんなしなやかな心をもった生き方を先生から学んだ1日だった。
タグ :ドイツ
2012年06月23日
日本も犬同伴のホテルが増える?
今日の新聞に「犬と一緒に宿泊できるホテルが増えている」という面白い記事が載っていた。日本では、長期休暇の支障は「ペット」。つまり、日本には犬を連れて宿泊できるホテルが少ないため、長期旅行は難しいと考えている飼い主が多いとのこと。
そういえばドイツにいるとき旅行は愛犬ブラッキーといつも一緒だった。ほとんどのホテルやペンションは犬もOK。もちろんブラッキーにも1泊7~10ユーロ位の宿泊料はかかったが・・ヨーロッパは陸続きなので、いろいろな国に車でブラッキーを連れて旅行に行った。ドライブインにはちょっとした散歩コースもあったり、犬用の水も用意してあったり。特に不便を感じたことはなかった。
もちろんイギリスやアイスランドなどは飛行機で行くので、その時はブラッキーはお留守番。ブリーダーさんのところにあずけていた。1週間で食事や散歩も込みで100ユーロぐらい払っていたかな。ブラッキーは、そこでボーダーコリーの仲間達と過ごした。親犬や兄弟たち(ブラッキーは8匹兄弟)もいて、安心してあずけられた。(ただ、ブリーダーさんがブラッキーの名前を忘れてしまい、「ボビ―」とか自分でつけて呼んでいて、10日ぶりに迎えに行ったとき「ブラッキー!」と呼んでも知らんぷりされた時には参った・・・)
日本に帰ってきて、数日の旅行に行こうと思い、近くの犬のペンションを調べたのだが、あまりの狭さにビックリ。これではストレスもたまりそう。さらにあまりの値段の高さにも驚き。
飼い主が犬をあずけて旅行に行きたくない気持ちもよくわかる。
犬同伴OKのホテルが日本にも増え、これから日本もヨーロッパのように犬同伴の旅行客が増えるのかな。
ホテルだけでなく、ドライブインにも散歩できるところがあったり、犬を連れていけるカフェやレストランも増えたらいいなあと思う。
夏暑い時に、車で待たせるなんてかわいそう。避暑地で一緒にブラッキーとカフェでお茶できたら楽しいだろうな。(ちなみにこれはドイツでは当たり前!!)
そして犬にとって居心地の良い快適なペンションがあったらいいな。
そういえばドイツにいるとき旅行は愛犬ブラッキーといつも一緒だった。ほとんどのホテルやペンションは犬もOK。もちろんブラッキーにも1泊7~10ユーロ位の宿泊料はかかったが・・ヨーロッパは陸続きなので、いろいろな国に車でブラッキーを連れて旅行に行った。ドライブインにはちょっとした散歩コースもあったり、犬用の水も用意してあったり。特に不便を感じたことはなかった。
もちろんイギリスやアイスランドなどは飛行機で行くので、その時はブラッキーはお留守番。ブリーダーさんのところにあずけていた。1週間で食事や散歩も込みで100ユーロぐらい払っていたかな。ブラッキーは、そこでボーダーコリーの仲間達と過ごした。親犬や兄弟たち(ブラッキーは8匹兄弟)もいて、安心してあずけられた。(ただ、ブリーダーさんがブラッキーの名前を忘れてしまい、「ボビ―」とか自分でつけて呼んでいて、10日ぶりに迎えに行ったとき「ブラッキー!」と呼んでも知らんぷりされた時には参った・・・)
日本に帰ってきて、数日の旅行に行こうと思い、近くの犬のペンションを調べたのだが、あまりの狭さにビックリ。これではストレスもたまりそう。さらにあまりの値段の高さにも驚き。
飼い主が犬をあずけて旅行に行きたくない気持ちもよくわかる。
犬同伴OKのホテルが日本にも増え、これから日本もヨーロッパのように犬同伴の旅行客が増えるのかな。
ホテルだけでなく、ドライブインにも散歩できるところがあったり、犬を連れていけるカフェやレストランも増えたらいいなあと思う。
夏暑い時に、車で待たせるなんてかわいそう。避暑地で一緒にブラッキーとカフェでお茶できたら楽しいだろうな。(ちなみにこれはドイツでは当たり前!!)
そして犬にとって居心地の良い快適なペンションがあったらいいな。
2012年06月21日
6月30日Egnlsih Cafe&Talk:形容詞に挑戦!
梅雨時うっとうしい日が続いていますが、English Cafe&Talk で頭をすっきりさせましょう!!
今回は、いろいろな形容詞に挑戦!「気の抜けたビール」はなんていうのかな?正解は"flat beer"
「ほら話」は? 英語では"a tall tale"
普段使っている形容詞が様々な意味が持っているのにびっくり!!
是非English Cafe&Talk のぞいてみてください。どなたでも大丈夫。大歓迎です!!
日時:6月30日(土)10:00~11:30
場所:武蔵野プレイス(JR中央線・武蔵境駅南口下車) 徒歩1分
http://www.musashino.or.jp/
1階Cafe フェルマータ(正面玄関を入ってすぐ左手にあります。一番奥の席をリザーブしています)
内容:1.質問コーナー
英語に関するあるゆる質問(表現、学習方法、コミュニケーションのとり方など)にお答えします。
2.英語で発信
自分が最近思ったこと、見たこと、感じたこと、行動したこと何でもよいので各自で英語で発信してみよう。
もちろんご一緒にわからない表現、言い回しなどを確認していきます。
3.いろいろな形容詞を使った表現に挑戦!!
講師:三浦優子
上智大学外国語学部英語科卒 米国ウィスコンシン州立大学交換留学
米国マンハッタンヴィルカレッジ大学院MAH修士
通訳、英語指導、海外生活アドバイザー
米・独生活15年。2010年日本に本帰国
参加費:1,500円
※Cafe フェルマータでのお飲み物代は各自負担になります。
定員:7名
申し込み・お問い合わせ
クロスカルチャーネットワーク
三浦
yukomiura05@yahoo.co.jp
Let's have fun!!
今回は、いろいろな形容詞に挑戦!「気の抜けたビール」はなんていうのかな?正解は"flat beer"
「ほら話」は? 英語では"a tall tale"
普段使っている形容詞が様々な意味が持っているのにびっくり!!
是非English Cafe&Talk のぞいてみてください。どなたでも大丈夫。大歓迎です!!
6月English Cafe &Talk
日時:6月30日(土)10:00~11:30
場所:武蔵野プレイス(JR中央線・武蔵境駅南口下車) 徒歩1分
http://www.musashino.or.jp/
1階Cafe フェルマータ(正面玄関を入ってすぐ左手にあります。一番奥の席をリザーブしています)
内容:1.質問コーナー
英語に関するあるゆる質問(表現、学習方法、コミュニケーションのとり方など)にお答えします。
2.英語で発信
自分が最近思ったこと、見たこと、感じたこと、行動したこと何でもよいので各自で英語で発信してみよう。
もちろんご一緒にわからない表現、言い回しなどを確認していきます。
3.いろいろな形容詞を使った表現に挑戦!!
講師:三浦優子
上智大学外国語学部英語科卒 米国ウィスコンシン州立大学交換留学
米国マンハッタンヴィルカレッジ大学院MAH修士
通訳、英語指導、海外生活アドバイザー
米・独生活15年。2010年日本に本帰国
参加費:1,500円
※Cafe フェルマータでのお飲み物代は各自負担になります。
定員:7名
申し込み・お問い合わせ
クロスカルチャーネットワーク
三浦
yukomiura05@yahoo.co.jp
Let's have fun!!
2012年06月19日
IB:日本語でも取得可に懸念
今日の新聞に「IB(国際バカロレア)が日本語でも取得できる見通しになった」という記事が載っていた。
英語ではなく日本語でIBがとれる。ただし、英語力を担保するため、一部の授業や試験は英語で実施するとある。何だか本末転倒なような気がする。そもそもIB実施校を日本で増やすというのは、海外も通用するグローバルな人材を育成するのが目的ではなかったのだろうか?
IBを日本語ではなく英語でとることに意味があるような気がする。原則英語なる授業を指導できる教員の確保が難しいためとあるが、日本語で取得となると、IB資格のための莫大な勉強量も半減し、つく力も半減してしまうと懸念する。
IB取得という結果論に力が入り、その過程が安易なものにかえられてしまうのは、問題だと思う。むしろ、英語で指導できる教員の強化に力をいれたほうが、今の日本人の英語力を伸ばし、グローバルな人材を輩出していく事につながるのではないだろうか?形だけ重んじるやり方には疑問を感じる。
英語ではなく日本語でIBがとれる。ただし、英語力を担保するため、一部の授業や試験は英語で実施するとある。何だか本末転倒なような気がする。そもそもIB実施校を日本で増やすというのは、海外も通用するグローバルな人材を育成するのが目的ではなかったのだろうか?
IBを日本語ではなく英語でとることに意味があるような気がする。原則英語なる授業を指導できる教員の確保が難しいためとあるが、日本語で取得となると、IB資格のための莫大な勉強量も半減し、つく力も半減してしまうと懸念する。
IB取得という結果論に力が入り、その過程が安易なものにかえられてしまうのは、問題だと思う。むしろ、英語で指導できる教員の強化に力をいれたほうが、今の日本人の英語力を伸ばし、グローバルな人材を輩出していく事につながるのではないだろうか?形だけ重んじるやり方には疑問を感じる。
タグ :IB
2012年06月18日
IBの要件:Extended Essay
今日本ではIB(国際バカロレア)取得のできる高校を増やすという動きがみられるが、IB取得条件の一つとしてExtended Essay がある。これは、研究課題を独自で決めて英文4,000字以内の学術論文にまとめる課題だ。通常生徒たちは、1年~2年かけてじっくり自分で調査・研究してまとめ上げていく。これにより自分で調べ考える、そして学術論文の書き方も身に付く。
先日日本のある高校でも「卒業論文」を書いているという記事を目にした。高校2年生から高校3年生の秋までに4万字以上の論文を書くという。これは大学受験を経験しない生徒対象、つまり私大への推薦入学コースにある独自教科「研究科」の授業での取り組みとのこと。生徒はまず「知らべ学習」から始め、テーマに迷い行き詰まりながら、論文に挑戦していく。
実際、IB取得は6科目の授業以外に、この"Extended Essay",そして”Theory of Knowledge"(2年間にわたる知識の理論の講義と演習)"CAS"(2年間の奉仕・スポーツ活動)とかなり苦しい。その中のこの課題論文は本当に大変だ。でも生徒たちは、自分の興味のある分野での論文をまとめ上げることによりかなりの達成感、充実感を味わうという。
日本の今の大学受験制度のもとではなかなかこのような学術論文を書くことは難しいだろうが、高校時代にこの課題論文に挑戦する価値は十分あると思う。
自分の私的好奇心、探究心、興味をもう一度見つめなおし、それを形にすることにより、その根底にあるものを掘り下げていくことができるのではないだろうか?真の学問の始まりのような気がする。
先日日本のある高校でも「卒業論文」を書いているという記事を目にした。高校2年生から高校3年生の秋までに4万字以上の論文を書くという。これは大学受験を経験しない生徒対象、つまり私大への推薦入学コースにある独自教科「研究科」の授業での取り組みとのこと。生徒はまず「知らべ学習」から始め、テーマに迷い行き詰まりながら、論文に挑戦していく。
実際、IB取得は6科目の授業以外に、この"Extended Essay",そして”Theory of Knowledge"(2年間にわたる知識の理論の講義と演習)"CAS"(2年間の奉仕・スポーツ活動)とかなり苦しい。その中のこの課題論文は本当に大変だ。でも生徒たちは、自分の興味のある分野での論文をまとめ上げることによりかなりの達成感、充実感を味わうという。
日本の今の大学受験制度のもとではなかなかこのような学術論文を書くことは難しいだろうが、高校時代にこの課題論文に挑戦する価値は十分あると思う。
自分の私的好奇心、探究心、興味をもう一度見つめなおし、それを形にすることにより、その根底にあるものを掘り下げていくことができるのではないだろうか?真の学問の始まりのような気がする。
タグ :IBExtended Essay
2012年06月16日
尊敬する先輩の生き方。
今日の夕刊をみてびっくり!!なんと英語通訳ガイド時代のずーっと尊敬していた先輩が大きく新聞に載っていたからだ。
そのコラムは現在活躍している人をとりあげ、仕事内容、週間スケジュールや余暇の過ごし方などを紹介している。先輩は25年近く通訳ガイドとして活躍し、今も現役ガイドで、後進の指導もしていらっしゃる。
私も本当に当時お世話になった。とにかくそのころから、仕事がずば抜けて出来、輝いていらして私のあこがれの人だった。
たまたま私が日本に10年ぶりに帰国してから、つい先日お会いしたばかりで、その時に今後の仕事についてもいろいろ相談にのっていただいた。一つ一つの言葉が胸に響いた。
なんとメイドカフェにも外人客を案内したり、自転車によるエコツアーなども取り入れ、知恵を絞りながら、外国のお客様をおもてなししていらっしゃるとのこと。いつまでも輝きを失わない先輩をみて、自分の仕事に誇りと自信を持ち、常にオープンマインドで新しい風を入れることが大切だと実感。私もこれからの自分の人生、信念を持ち、しなやかな心を持って進んでいきたい。
先輩、いつまでも応援しています!!
そのコラムは現在活躍している人をとりあげ、仕事内容、週間スケジュールや余暇の過ごし方などを紹介している。先輩は25年近く通訳ガイドとして活躍し、今も現役ガイドで、後進の指導もしていらっしゃる。
私も本当に当時お世話になった。とにかくそのころから、仕事がずば抜けて出来、輝いていらして私のあこがれの人だった。
たまたま私が日本に10年ぶりに帰国してから、つい先日お会いしたばかりで、その時に今後の仕事についてもいろいろ相談にのっていただいた。一つ一つの言葉が胸に響いた。
なんとメイドカフェにも外人客を案内したり、自転車によるエコツアーなども取り入れ、知恵を絞りながら、外国のお客様をおもてなししていらっしゃるとのこと。いつまでも輝きを失わない先輩をみて、自分の仕事に誇りと自信を持ち、常にオープンマインドで新しい風を入れることが大切だと実感。私もこれからの自分の人生、信念を持ち、しなやかな心を持って進んでいきたい。
先輩、いつまでも応援しています!!
タグ :通訳案内士
2012年06月13日
スープは食べる!
今週は、ラジオ英会話で「日本の習慣」についてのテーマを扱っていて、それに関するいろいろな表現が出てくる。
そして今日の表現は:
"It's a Japanese custom to slurp your noodles."
「音を立てて麺をすするのが日本の習慣です。」という文だ。
確かに日本に帰国してまず気が付いたのは、おそばをすする音だった。妙に懐かしく「日本に帰ってきたんだな~」と思ったものだ。以前、ある落語家が、話の中でおそばを食べる場面ををおいしそうに音を立てて話していたのを聞いたことがある。
でもおそばの時には音を立てていいのに、スープの時は音を立てないで飲むのが食事のマナー。
確かに欧米では、音を立てて飲むのを聞いたことがない。スープは「飲む」と日本語でいうが、英語は"eat soup"で"drink soup"とは言わない。そしてさらに面白いのは、ドイツ語でも英語と同様に、"Suppe essen"(食べる)と表現し、「飲む」という"trinken"とは言わない。
おそばの時には音とを立てていいのに、スープの時は音をたてないように、食べるようにして飲む。
なかなかむずかしい!!
そして今日の表現は:
"It's a Japanese custom to slurp your noodles."
「音を立てて麺をすするのが日本の習慣です。」という文だ。
確かに日本に帰国してまず気が付いたのは、おそばをすする音だった。妙に懐かしく「日本に帰ってきたんだな~」と思ったものだ。以前、ある落語家が、話の中でおそばを食べる場面ををおいしそうに音を立てて話していたのを聞いたことがある。
でもおそばの時には音を立てていいのに、スープの時は音を立てないで飲むのが食事のマナー。
確かに欧米では、音を立てて飲むのを聞いたことがない。スープは「飲む」と日本語でいうが、英語は"eat soup"で"drink soup"とは言わない。そしてさらに面白いのは、ドイツ語でも英語と同様に、"Suppe essen"(食べる)と表現し、「飲む」という"trinken"とは言わない。
おそばの時には音とを立てていいのに、スープの時は音をたてないように、食べるようにして飲む。
なかなかむずかしい!!
タグ :日本の習慣
2012年06月13日
腹筋力の少ない(?)ブラッキー!
今日jazz vocalのレッスンで、いつものように歌う前の準備体操や発声練習をしたのだが、先生が「今日は犬がが吠えるのをまねして発声してみましょう!」とおっしゃった。
「ワンワン」と犬の吠え方を真似するのだが、これがかなりおなかの力を入れて発声しないとそれらしく聞こえない。ということは、犬もほえるとき、しっかりした腹筋を使っているということが判明!!
そういえば、ほとんどほえない我が家の愛犬ブラッキーも寝ているときに時々「ウーワンワン!」と寝言のようにほえるときがある。その時よく見るとブラッキーのおなかがかなりゆれ動いていた!!のを見たことがある。それにしてもあまりほえないブラッキーは腹筋力がきちんとついているのだろうか?なんだか心配になった。
水泳のレッスンでもおなかに力を入れて泳ぐように言われた。そうするとバランスがよく取れて体が傾かず泳ぐことができる。ウォーキングの時もおなかにぐっと力を入れて歩くとよいことも聞いたことがある。バランスの良い健康な体作りには腹筋が大事??となると犬もそうなのかな?
よく吠える犬は健康??なのかな。ブラッキーもう少し吠えていいんだよ・・・
「ワンワン」と犬の吠え方を真似するのだが、これがかなりおなかの力を入れて発声しないとそれらしく聞こえない。ということは、犬もほえるとき、しっかりした腹筋を使っているということが判明!!
そういえば、ほとんどほえない我が家の愛犬ブラッキーも寝ているときに時々「ウーワンワン!」と寝言のようにほえるときがある。その時よく見るとブラッキーのおなかがかなりゆれ動いていた!!のを見たことがある。それにしてもあまりほえないブラッキーは腹筋力がきちんとついているのだろうか?なんだか心配になった。
水泳のレッスンでもおなかに力を入れて泳ぐように言われた。そうするとバランスがよく取れて体が傾かず泳ぐことができる。ウォーキングの時もおなかにぐっと力を入れて歩くとよいことも聞いたことがある。バランスの良い健康な体作りには腹筋が大事??となると犬もそうなのかな?
よく吠える犬は健康??なのかな。ブラッキーもう少し吠えていいんだよ・・・
2012年06月12日
マスクをしないドイツ人??
ドイツで10年生活している間、マスクをしている人を見かけたことはほとんどない。ところが日本に帰国してから、冬の時期や花粉が舞う春には、マスクをしている人をたくさん見かけた。もちろんドイツ人も風邪をひくし、花粉症の人はいる。でもどういうわけか、マスクをする習慣がないようで、マスク姿を全くと言っていいくらい目にしなかった。
マスクは偉大だ。風邪をひいたときもマスクをすればほかの人に菌をまき散らすことを防げるし、自分もかなり楽。先日風邪をひいたらしくて、のどがひりひり。外出時に、乾燥した中で、マスクをするとかなりのども痛みがやわらいだ。
ドイツにいるときも大掃除の時に家の中でマスクをしようと思い、薬局屋にマスクを買いに行った。ところが売っているのは、外科の先生が手術時にするようなマスクしかなく、1,2枚入ってかなりの値段だった。それ以来、日本に一時帰国するたびにマスクを買って帰ったものだ。
日本に帰り、人目を気にせずマスクができるのがうれしい!!
それにしてもどうしてドイツ人はマスクをしないのかな?便利だと思うのだが。今度是非聞いてみよう。
マスクは偉大だ。風邪をひいたときもマスクをすればほかの人に菌をまき散らすことを防げるし、自分もかなり楽。先日風邪をひいたらしくて、のどがひりひり。外出時に、乾燥した中で、マスクをするとかなりのども痛みがやわらいだ。
ドイツにいるときも大掃除の時に家の中でマスクをしようと思い、薬局屋にマスクを買いに行った。ところが売っているのは、外科の先生が手術時にするようなマスクしかなく、1,2枚入ってかなりの値段だった。それ以来、日本に一時帰国するたびにマスクを買って帰ったものだ。
日本に帰り、人目を気にせずマスクができるのがうれしい!!
それにしてもどうしてドイツ人はマスクをしないのかな?便利だと思うのだが。今度是非聞いてみよう。
2012年06月10日
日本人としてのアイデンティティー?
先日、母校の大学で「今後の日本の英語教育ー「国際語としての英語力向上のための5つの提言」が目指すもの」という内容の講義を聞く機会があった。その中で政府の「グローバル人材育成推進会議の中間まとめ」のなかに「グローバル人材」の概念要素のひとつとして、「異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー」という項目があった。
この中の「日本人としてのアイデンティティー」という言葉にふと疑問を持った。
米・独に15年暮らして日本に帰国した今、日本の文化を異文化ととらえている自分がいる。そして今までの海外生活から身につけた価値観を完全に捨てて日本の文化に同化するのではなく異文化から学んだことをよい形でうまく生かしていこうと思っている。日本に帰国が決まったとき、英・独・仏語を話すベルギー人女性から、「日本に帰っても自分を変える(change)のではなく適応(adjust)すればよい」と言われた。この言葉を聞いて、ほっとした。長い間、日本を離れて海外で暮らし、日本でうまくやっていけるのか、不安があったからだ。今は日本を異文化としてとらえると気が楽になる。私の中では日本と外国の違いを認識して、それをよい形で生かしていくという気持ちが強く、あまり「日本人としてのアイデンティティー」を意識して生活していない。
同じ日本人でも様々な価値観や考え方を持った人がいる。あまりこの「日本人としてのアイデンティティー」を強く意識せず、もっと異文化と自国の文化の違いを客観的にとらえ、よい形で両方を共存させていく柔軟な生き方でもよいのではないだろうか?
この中の「日本人としてのアイデンティティー」という言葉にふと疑問を持った。
米・独に15年暮らして日本に帰国した今、日本の文化を異文化ととらえている自分がいる。そして今までの海外生活から身につけた価値観を完全に捨てて日本の文化に同化するのではなく異文化から学んだことをよい形でうまく生かしていこうと思っている。日本に帰国が決まったとき、英・独・仏語を話すベルギー人女性から、「日本に帰っても自分を変える(change)のではなく適応(adjust)すればよい」と言われた。この言葉を聞いて、ほっとした。長い間、日本を離れて海外で暮らし、日本でうまくやっていけるのか、不安があったからだ。今は日本を異文化としてとらえると気が楽になる。私の中では日本と外国の違いを認識して、それをよい形で生かしていくという気持ちが強く、あまり「日本人としてのアイデンティティー」を意識して生活していない。
同じ日本人でも様々な価値観や考え方を持った人がいる。あまりこの「日本人としてのアイデンティティー」を強く意識せず、もっと異文化と自国の文化の違いを客観的にとらえ、よい形で両方を共存させていく柔軟な生き方でもよいのではないだろうか?
2012年06月07日
何でも自分でやってしまうドイツ人!!
ドイツに10年いる間、感じたことはドイツの人は何でも自分でやってしまうことだ。一番驚いたのは、娘が通っていたドイツの幼稚園での引っ越しの時だ。幼稚園が広い敷地に移ることになって、その準備ということで父兄が皆集まったのだが、なんとほとんどすべてを専門業者に頼まず自分たちでやってしまったのだ。つまり、電気の配線、壁塗り、幼稚園で使う机やいす、ほぼあらゆることを自分たちで用意する。父兄の中には電気屋さんや芸術家のお父さんたちもいたのだが、皆で協力し合ってあっという間に準備をしてしまったのには本当にびっくり。そしてさらにお母さんたちも元気元気!!私はお手伝い感覚でエプロンを持って行ったのだが、皆、白のつなぎルック。あるお母さんの壁塗りの上手なこと!!
これはやはり子供のころからの教育にも関係していると思う。日本人は手先が器用ということだが、ドイツ人もそれに劣らず本当に器用だと思う。娘が幼稚園時代に作った数々の手作り作品。小学校時代にも母の日や父の日などもいろいろな作品を作り親にプレゼントしたりもする。そのほかにも自分でキャンドルを作ったり、飛び出す絵本を作ったり・・・・・
私のドイツの友達のなかにもクリスマスカードを手作りしたり、プレゼント用に実にきれいな紙の袋を作る人もいる。
自分でものを作ったり、すべて自分で修理したり…そういえば、自転車の修理までしてしまうドイツの友達がいて、いつも彼女のところにパンクした自転車を持って行って直してもらっていた。
そんな感覚は日本人にはあまりないと思う。少なくとも物が壊れたら、すぐに修理屋さんに頼んでしまう私には驚きだった。
元気で器用なドイツ人!!
見習うことが一杯ある。
これはやはり子供のころからの教育にも関係していると思う。日本人は手先が器用ということだが、ドイツ人もそれに劣らず本当に器用だと思う。娘が幼稚園時代に作った数々の手作り作品。小学校時代にも母の日や父の日などもいろいろな作品を作り親にプレゼントしたりもする。そのほかにも自分でキャンドルを作ったり、飛び出す絵本を作ったり・・・・・
私のドイツの友達のなかにもクリスマスカードを手作りしたり、プレゼント用に実にきれいな紙の袋を作る人もいる。
自分でものを作ったり、すべて自分で修理したり…そういえば、自転車の修理までしてしまうドイツの友達がいて、いつも彼女のところにパンクした自転車を持って行って直してもらっていた。
そんな感覚は日本人にはあまりないと思う。少なくとも物が壊れたら、すぐに修理屋さんに頼んでしまう私には驚きだった。
元気で器用なドイツ人!!
見習うことが一杯ある。
タグ :ドイツ人
2012年06月07日
"・・・ wrong side of the bed ?"
今日聞いた「実践ビジネス英語」の中に懐かしい慣用句が出てきた。"in someone's shoes"
誰かの靴の中に?????これは、英語の慣用句で「人の立場になって」という意味である。アメリカの大学に交換留学していた時に友達に言われ、まったく意味が分からず唖然!!どうして靴がでてくるの????
そしてもうひとつ忘れられない慣用句がある。留学中、寮に入っていて、アメリカ人のルームメイトから朝、言われた言葉。
"You got up on the wrong side of the bed!"ベッドの間違えた場所にいる????私はちゃんとベッドの真ん中にいるのに???
これも意味がわからず、ねぼけているのかな~とおもいきや、「寝起きが悪い、朝から、虫の居所が悪い」という意味。
英語にもこんなおもしろい慣用句がたくさんある。地道に少しずつ楽しみながら、覚えていくしかないかな。
誰かの靴の中に?????これは、英語の慣用句で「人の立場になって」という意味である。アメリカの大学に交換留学していた時に友達に言われ、まったく意味が分からず唖然!!どうして靴がでてくるの????
そしてもうひとつ忘れられない慣用句がある。留学中、寮に入っていて、アメリカ人のルームメイトから朝、言われた言葉。
"You got up on the wrong side of the bed!"ベッドの間違えた場所にいる????私はちゃんとベッドの真ん中にいるのに???
これも意味がわからず、ねぼけているのかな~とおもいきや、「寝起きが悪い、朝から、虫の居所が悪い」という意味。
英語にもこんなおもしろい慣用句がたくさんある。地道に少しずつ楽しみながら、覚えていくしかないかな。
タグ :英語慣用句
2012年06月03日
大丈夫?「飛び入学」?
今日の新聞に「文部科学省が高校を最短2年で卒業できる制度を創設する方針を決定」という記事が掲載されていた。
いわゆる大学への「飛び入学制度」だ。
ドイツでも小学校への「飛び入学」や学年をスキップする「飛び級」がある。娘が6歳でドイツ現地校に入学した時、クラスの年齢は4歳、5歳、6歳とまちまちであった。通常は、6月の時点で6歳になった子供が小学校1年生になるのだが、子供の能力次第で6歳よりも早く入学できるようになっている。娘のクラスも全く違和感なくスタートした感じだった。ただ学年が上がるにつれて、やはり精神面で少し成長度合いに違いが出てきたようで、「飛び入学」した子供達は学力面ではすぐれているが、精神面や生活面でほかの子供たちと足並みがそろわず、友達ができにくいなどのケースがあったようだ。
このように「飛び入学」や「飛び級」のケースは成績優秀という学力面だけでなく、メンタルな面でのケアーが今以上に必要であると感じる。
東大の秋入学にしても飛び入学にしても制度がどんどん先走りしているようで、メンタル面を含め様々なケアーにあまり目が向けられていないような気がするのだが・・・・・
いわゆる大学への「飛び入学制度」だ。
ドイツでも小学校への「飛び入学」や学年をスキップする「飛び級」がある。娘が6歳でドイツ現地校に入学した時、クラスの年齢は4歳、5歳、6歳とまちまちであった。通常は、6月の時点で6歳になった子供が小学校1年生になるのだが、子供の能力次第で6歳よりも早く入学できるようになっている。娘のクラスも全く違和感なくスタートした感じだった。ただ学年が上がるにつれて、やはり精神面で少し成長度合いに違いが出てきたようで、「飛び入学」した子供達は学力面ではすぐれているが、精神面や生活面でほかの子供たちと足並みがそろわず、友達ができにくいなどのケースがあったようだ。
このように「飛び入学」や「飛び級」のケースは成績優秀という学力面だけでなく、メンタルな面でのケアーが今以上に必要であると感じる。
東大の秋入学にしても飛び入学にしても制度がどんどん先走りしているようで、メンタル面を含め様々なケアーにあまり目が向けられていないような気がするのだが・・・・・
2012年06月01日
Vastness:英語の世界
先日参加した1日「英語教授法セミナー」で、とてもユニーク(?)な話を米国人大学教授から聞いた。
彼は、以前、これからアメリカのビジネス界で仕事をするという日本人にインテンシブにビジネス英語を教えていたとのこと。その授業は、ロールプレイのやり方で、AとBという対話形式による練習で、何度もいろいろな場面設定で行ったとのこと。
そして、その日本人の方がアメリカに行き半年後に日本に帰国。「いかがでしたか?」との先生の問いに、「先生から習ったことは全く役に立たなくて、散散でした。相手からは、私が先生から習ったような返答がきませんでしたから。」と日本の方。
これは信じられないような話だが、本当にあったことらしい。それにしても授業でロールプレイしたのと同じように相手の応答がかえってくることはむしろ少ない。英語学習上、さまざまな対話練習をするが、あくまでも一例に過ぎない。flexible,spontaneousな対応が求められる。
本当に言葉はVastnessな世界だと実感する。
彼は、以前、これからアメリカのビジネス界で仕事をするという日本人にインテンシブにビジネス英語を教えていたとのこと。その授業は、ロールプレイのやり方で、AとBという対話形式による練習で、何度もいろいろな場面設定で行ったとのこと。
そして、その日本人の方がアメリカに行き半年後に日本に帰国。「いかがでしたか?」との先生の問いに、「先生から習ったことは全く役に立たなくて、散散でした。相手からは、私が先生から習ったような返答がきませんでしたから。」と日本の方。
これは信じられないような話だが、本当にあったことらしい。それにしても授業でロールプレイしたのと同じように相手の応答がかえってくることはむしろ少ない。英語学習上、さまざまな対話練習をするが、あくまでも一例に過ぎない。flexible,spontaneousな対応が求められる。
本当に言葉はVastnessな世界だと実感する。
タグ :英語学習
2012年06月01日
”Not enough"
先日の英語教授法セミナーで”Not every"以外にもう一つ米国大学教授が指摘されたことは”Not enough"ということだった。
つまり、英語の学習はそれこそ際限なく、単語にしても日々新しい単語や用語が出てくる。それを完全に身につけることは英語母国語者にとっても難しい。ましてや英語学習者には、あまりにも学習範囲が広すぎる。"Vastness of Language"
言葉の学習は手におえないほど広い世界だ。完全に充分言葉を知ることはありえない。その事実を認識することにより、英語学習もむしろ効果的にできると思う。
たとえば、単語をすべて覚える代わりに"circumlocution"を使うことにより、限られた単語力でもコミュニケーションをとることは可能だ。あるものを説明するのにその単語を知らないとする。その場合、それが、どのような形や色をしていて、どういう目的で使うかなど説明すれば、相手に伝わる事が多い。
また、病名などの専門単語を知らなくても、"inflammation"(炎症)という単語さえ知っていれば、それに炎症をしている場所の単語を組み合わせ説明できる。
この"circumlocution"は、実際に英語のコミュニケーション能力を高める学習法のひとつとしても使うことができる。
際限のない永遠に終わりのない言葉の学習。"Not enough"という現実を見据え、そのうえでいかに効果的に言葉を学ぶかを考えていくことが大切だと思う。
つまり、英語の学習はそれこそ際限なく、単語にしても日々新しい単語や用語が出てくる。それを完全に身につけることは英語母国語者にとっても難しい。ましてや英語学習者には、あまりにも学習範囲が広すぎる。"Vastness of Language"
言葉の学習は手におえないほど広い世界だ。完全に充分言葉を知ることはありえない。その事実を認識することにより、英語学習もむしろ効果的にできると思う。
たとえば、単語をすべて覚える代わりに"circumlocution"を使うことにより、限られた単語力でもコミュニケーションをとることは可能だ。あるものを説明するのにその単語を知らないとする。その場合、それが、どのような形や色をしていて、どういう目的で使うかなど説明すれば、相手に伝わる事が多い。
また、病名などの専門単語を知らなくても、"inflammation"(炎症)という単語さえ知っていれば、それに炎症をしている場所の単語を組み合わせ説明できる。
この"circumlocution"は、実際に英語のコミュニケーション能力を高める学習法のひとつとしても使うことができる。
際限のない永遠に終わりのない言葉の学習。"Not enough"という現実を見据え、そのうえでいかに効果的に言葉を学ぶかを考えていくことが大切だと思う。
タグ :英語学習