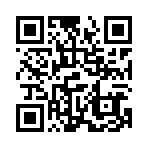2023年04月28日
親も頑張っているよ!
Hi, everyone! How are you doing?
先日、とても面白い記事を読みました。それは、台湾人の作家、温又柔(おん・ゆうじゅう)さんの記事です。彼女は台湾で生まれましたが、3歳の時に親とともに来日しているので、日本語育ちです。その記事の中で思春期を迎えた温さんが、自分の母親の話す日本語を聞いて、「なんで、そんな変な日本語をしゃべるの?もっとちゃんと喋ってよ」ととがめたとありました 母親は、日本で生活をするために必死で日本語を話していたわけですが、温さんにとっては、変な日本語に聞こえたのでしょう。私自身も、家族でドイツで生活を始めてから、大人になってからドイツ語に触れたので、ドイツ語で生活するのに大変でした。一方、子どもは現地幼稚園、現地校に通い、どんどんドイツ語が上手になり、時々、わたしがドイツの友達と話しているときに、子どもから、今の受け答えおかしかったよ、と言われ、たじたじになったこともありました。温さんのお母さんも、温さんのきつい言葉??に涙ぐんでいたそうです。その気持ち、わかる気がします。実は、同じような場面に、今年渡独した時に遭遇しました。家の近くのパン屋さんでカフェをしているとき、小学生低学年の中国人の女の子が、中国人のお母さんと一緒に入ってきて、私の横の席に座りました。二人の会話はほぼ中国語でしたが、時折、ドイツ語も聞こえてきます。もちろん女の子は、流ちょうなドイツ語(ドイツの学校に通っているのでしょう)、それに対してお母さんは、たどたどしいドイツ語。それでも一生けん命、子どもと話しているので、私が「お母さん、ドイツ語、がんばっているね~」と女の子に話しかけました。するとその女の子は、なんと「でもお母さんのドイツ語、なんだか変!」と笑いながら、言ったのです。お母さんは、思わず苦笑い。海外に住み、家族で生活を始めると、子どもたちは、現地校に行ったりして、みるみるうちに言語を習得していきます。少なくとも話し言葉に関しては。親の方は、それに追いつきません。そんなわけで私も含め、その中国人のお母さん、そして、温さんのお母さんたちは、こどもたちに頭が上がりません。でも、親たちも頑張っているんですよ~(笑)。暖かく見守ってほしいなあ。まあ、無理かな。子どもたちは正直で時に、厳しいですね!!
先日、とても面白い記事を読みました。それは、台湾人の作家、温又柔(おん・ゆうじゅう)さんの記事です。彼女は台湾で生まれましたが、3歳の時に親とともに来日しているので、日本語育ちです。その記事の中で思春期を迎えた温さんが、自分の母親の話す日本語を聞いて、「なんで、そんな変な日本語をしゃべるの?もっとちゃんと喋ってよ」ととがめたとありました 母親は、日本で生活をするために必死で日本語を話していたわけですが、温さんにとっては、変な日本語に聞こえたのでしょう。私自身も、家族でドイツで生活を始めてから、大人になってからドイツ語に触れたので、ドイツ語で生活するのに大変でした。一方、子どもは現地幼稚園、現地校に通い、どんどんドイツ語が上手になり、時々、わたしがドイツの友達と話しているときに、子どもから、今の受け答えおかしかったよ、と言われ、たじたじになったこともありました。温さんのお母さんも、温さんのきつい言葉??に涙ぐんでいたそうです。その気持ち、わかる気がします。実は、同じような場面に、今年渡独した時に遭遇しました。家の近くのパン屋さんでカフェをしているとき、小学生低学年の中国人の女の子が、中国人のお母さんと一緒に入ってきて、私の横の席に座りました。二人の会話はほぼ中国語でしたが、時折、ドイツ語も聞こえてきます。もちろん女の子は、流ちょうなドイツ語(ドイツの学校に通っているのでしょう)、それに対してお母さんは、たどたどしいドイツ語。それでも一生けん命、子どもと話しているので、私が「お母さん、ドイツ語、がんばっているね~」と女の子に話しかけました。するとその女の子は、なんと「でもお母さんのドイツ語、なんだか変!」と笑いながら、言ったのです。お母さんは、思わず苦笑い。海外に住み、家族で生活を始めると、子どもたちは、現地校に行ったりして、みるみるうちに言語を習得していきます。少なくとも話し言葉に関しては。親の方は、それに追いつきません。そんなわけで私も含め、その中国人のお母さん、そして、温さんのお母さんたちは、こどもたちに頭が上がりません。でも、親たちも頑張っているんですよ~(笑)。暖かく見守ってほしいなあ。まあ、無理かな。子どもたちは正直で時に、厳しいですね!!
タグ :言語親子コミュニケーション
2023年04月26日
失敗から学ぶ新たな挑戦!
Hi, everyone! It was very chilly today, wasn't it?
今日の新聞記事に、日本の宇宙企業アイスペースが、世界で民間企業初となる月着陸を目指していたが、その目標が達成できなかった、とありました。私も是非成功したらよいなと希望を持っていたので、とても残念に思いました。でも、そのあとに、創業当初から技術面で支えてきた東北大学の吉田教授の「失敗なくして成功はない。今回得られた教訓やデータを生かし、挑戦を続けて欲しい」という言葉を目にして、なんだかとてもジーンときました。私自身、今まで、失敗することが怖くて、二の足を踏むことがありました。確かに失敗をあまりしたくない、できるだけ避けたいと思いがちですが、失敗から学ぶことはとても多いと思います。また、「失敗」ではないですが、大学の語学の授業において、学生たちは、間違うことを恐れて、どうも完璧な正しい英語を話すことに重きをおきがちです。ですから、わたしからはいつも「間違いを恐れることはない。むしろ、たくさん、間違いをしてください! 間違えたら、それを直していけばよいのです。ただそれだけのことです。」と伝えています。学生にそのようなメッセージを送っている私ですが、なんと、どうやら失敗や間違いを恐れている自分がいるようです。吉田教授の言葉を目にして、これからは、失敗や間違いを恐れず、そこから学んでいこう、それが成功につながるんだ、という意識を持ち続けようと強く思いました。
今日の新聞記事に、日本の宇宙企業アイスペースが、世界で民間企業初となる月着陸を目指していたが、その目標が達成できなかった、とありました。私も是非成功したらよいなと希望を持っていたので、とても残念に思いました。でも、そのあとに、創業当初から技術面で支えてきた東北大学の吉田教授の「失敗なくして成功はない。今回得られた教訓やデータを生かし、挑戦を続けて欲しい」という言葉を目にして、なんだかとてもジーンときました。私自身、今まで、失敗することが怖くて、二の足を踏むことがありました。確かに失敗をあまりしたくない、できるだけ避けたいと思いがちですが、失敗から学ぶことはとても多いと思います。また、「失敗」ではないですが、大学の語学の授業において、学生たちは、間違うことを恐れて、どうも完璧な正しい英語を話すことに重きをおきがちです。ですから、わたしからはいつも「間違いを恐れることはない。むしろ、たくさん、間違いをしてください! 間違えたら、それを直していけばよいのです。ただそれだけのことです。」と伝えています。学生にそのようなメッセージを送っている私ですが、なんと、どうやら失敗や間違いを恐れている自分がいるようです。吉田教授の言葉を目にして、これからは、失敗や間違いを恐れず、そこから学んでいこう、それが成功につながるんだ、という意識を持ち続けようと強く思いました。
2023年04月24日
偏りなく、さまざまな英語に触れる
Hi, everyone!How have you been?
今日は、英語について最近感じていることを書いてみます。日本では、英語学習というとまだまだアメリカ英語が主流のように思います。NHKの語学番組にしても学校の教育現場で使われる音声データにしてもアメリカ英語を耳にすることが多いような気がします。でも実際に英語にはイギリス英語、オーストラリア英語、カナダ英語、ニュージーランド英語など様々な英語があります。大学生が受験するTOEIC試験においてもリスニングパートではいろいろな国の英語が使われています。先日、クラスの学生たちにリスニング・パートの英語について聞いたところ、イギリス英語は聞き取りにくい、とぼやいていました。きっと中・高校時代に、アメリカ英語に多く触れてきたからなのでしょう。さらに、英語を母国語としない人々は、英語母国語話者よりはるかに多いわけです。そうなるとお互いの共通言語は英語になるわけで、英語でコミュニケーションをとる必要性が出てきます。たまたま、今日の「ニュースで学ぶ現代英語」の番組で、NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長の英語による声明を取り上げていました。彼の英語は、発音が大変明瞭で、語句と語句の間にしっかりと区切りを入れているのでとても聞き取りやすいものでした。これからのグローバル化時代には、アメリカ英語に偏ることなく、さまざまな英語に触れ、堂々と明瞭な英語でコミュニケーションをすることがとても大切だと思いました。

あまりの美しさに思わず写真をとりました!
今日は、英語について最近感じていることを書いてみます。日本では、英語学習というとまだまだアメリカ英語が主流のように思います。NHKの語学番組にしても学校の教育現場で使われる音声データにしてもアメリカ英語を耳にすることが多いような気がします。でも実際に英語にはイギリス英語、オーストラリア英語、カナダ英語、ニュージーランド英語など様々な英語があります。大学生が受験するTOEIC試験においてもリスニングパートではいろいろな国の英語が使われています。先日、クラスの学生たちにリスニング・パートの英語について聞いたところ、イギリス英語は聞き取りにくい、とぼやいていました。きっと中・高校時代に、アメリカ英語に多く触れてきたからなのでしょう。さらに、英語を母国語としない人々は、英語母国語話者よりはるかに多いわけです。そうなるとお互いの共通言語は英語になるわけで、英語でコミュニケーションをとる必要性が出てきます。たまたま、今日の「ニュースで学ぶ現代英語」の番組で、NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長の英語による声明を取り上げていました。彼の英語は、発音が大変明瞭で、語句と語句の間にしっかりと区切りを入れているのでとても聞き取りやすいものでした。これからのグローバル化時代には、アメリカ英語に偏ることなく、さまざまな英語に触れ、堂々と明瞭な英語でコミュニケーションをすることがとても大切だと思いました。

あまりの美しさに思わず写真をとりました!
2023年04月22日
探求心を持ち続ける!
Hi, everyone! How is it going?
今日は、久しぶりに私の属している学会の研究会にオンラインライン参加しました。今日の登壇者は今年、博士論文が受諾され、博士号をとった大学院時代の知人でした。私より、2年後に博士課程に入学した彼女ですが、5年程かけ、無事に博士論文を書き上げました。途中であきらめずに最後まで頑張った彼女は本当に素晴らしいと思います。博士課程に入学したものの、残念ながら、途中で挫折してしまう人もいます。学費捻出のため、アルバイトをせざるを得ず、それが忙しくなり論文に費やす時間がなくなり在籍期間を越えてしまう人、研究が思うようにいかずに諦めてしまう人、重圧に押しつぶされてしまう人など。私自身も論文作成中の何年間は、好きな本も読めず、読むのは、ひたすら論文関連の文献だけ、友達に会うのも好きな映画をみるのも、論文のことが気になり封印しました。すべてが博論を書き上げることを中心に回っていたような気がします。博士論文を書き上げるのは、自分との戦いのように感じていました。論文に向き合い続けるには、自分の中に強い思いが不可欠と思います。今日、発表した彼女の場合の場合は、自分があるグループに出会ったときに受けた「強い衝撃」、それが一体何であったのか、それを突き止めることが大きな目的であったといいます。その強い気持ちが彼女の研究活動を前へ前へと推し進めていったのだと思います。研究者にとってあることを探求する強い気持ちは本当に大切なものなのだと実感しました。
今日の彼女の発表を聞き、大変刺激を受けました。研究だけでなく、毎日の生活の中でも常に探求心を持ち続けたいと強く思いました。でも、もちろん、今度は、好きなことは封印せず、楽しみながら、やっていけたらいいなあと思っています!
今日は、久しぶりに私の属している学会の研究会にオンラインライン参加しました。今日の登壇者は今年、博士論文が受諾され、博士号をとった大学院時代の知人でした。私より、2年後に博士課程に入学した彼女ですが、5年程かけ、無事に博士論文を書き上げました。途中であきらめずに最後まで頑張った彼女は本当に素晴らしいと思います。博士課程に入学したものの、残念ながら、途中で挫折してしまう人もいます。学費捻出のため、アルバイトをせざるを得ず、それが忙しくなり論文に費やす時間がなくなり在籍期間を越えてしまう人、研究が思うようにいかずに諦めてしまう人、重圧に押しつぶされてしまう人など。私自身も論文作成中の何年間は、好きな本も読めず、読むのは、ひたすら論文関連の文献だけ、友達に会うのも好きな映画をみるのも、論文のことが気になり封印しました。すべてが博論を書き上げることを中心に回っていたような気がします。博士論文を書き上げるのは、自分との戦いのように感じていました。論文に向き合い続けるには、自分の中に強い思いが不可欠と思います。今日、発表した彼女の場合の場合は、自分があるグループに出会ったときに受けた「強い衝撃」、それが一体何であったのか、それを突き止めることが大きな目的であったといいます。その強い気持ちが彼女の研究活動を前へ前へと推し進めていったのだと思います。研究者にとってあることを探求する強い気持ちは本当に大切なものなのだと実感しました。
今日の彼女の発表を聞き、大変刺激を受けました。研究だけでなく、毎日の生活の中でも常に探求心を持ち続けたいと強く思いました。でも、もちろん、今度は、好きなことは封印せず、楽しみながら、やっていけたらいいなあと思っています!
2023年04月19日
ストレスを受けたトマトが声,voice ,を出す!
Hi, everyone! How are you doing?
先日、「ニュースで学ぶ現代英語」というラジオ番組で、「ストレスを受けたトマトが声を出す」という衝撃的な内容のニュースを紹介していました。イスラエルの科学者たちが、トマトを防音の箱に入れ、さまざまな種類のストレスにさらしました。例えば、茎を切りとったり、水を与えなかったり。そしてトマトに聴音波マイクを当ててみると「ポツ、ポツ、ポツ」という音が聞こえたそうです。もちろん、音は、通常、高すぎて、人間には聞こえませんが、その周波数を調整するとそのような音が聞こえたそうです。音が出るメカニズムははっきりしていませんが、水が通る管が乾燥した茎の中で壊れる時に、気泡が発生し、それが関係しているのではないか、と分析しています。このニュースを聞いてから、トマトも含め、あらゆる野菜を大切にいただこうと思いました。時々、買いすぎたり、食べ忘れたリして、冷蔵庫の中にしなびて残ってしまっている野菜たちがいます。これからは、そのようなことがないようにしっかりといただく。ストレスを抱えたトマトや野菜にたいして、私たちができる唯一の恩返しだと思います。
先日、「ニュースで学ぶ現代英語」というラジオ番組で、「ストレスを受けたトマトが声を出す」という衝撃的な内容のニュースを紹介していました。イスラエルの科学者たちが、トマトを防音の箱に入れ、さまざまな種類のストレスにさらしました。例えば、茎を切りとったり、水を与えなかったり。そしてトマトに聴音波マイクを当ててみると「ポツ、ポツ、ポツ」という音が聞こえたそうです。もちろん、音は、通常、高すぎて、人間には聞こえませんが、その周波数を調整するとそのような音が聞こえたそうです。音が出るメカニズムははっきりしていませんが、水が通る管が乾燥した茎の中で壊れる時に、気泡が発生し、それが関係しているのではないか、と分析しています。このニュースを聞いてから、トマトも含め、あらゆる野菜を大切にいただこうと思いました。時々、買いすぎたり、食べ忘れたリして、冷蔵庫の中にしなびて残ってしまっている野菜たちがいます。これからは、そのようなことがないようにしっかりといただく。ストレスを抱えたトマトや野菜にたいして、私たちができる唯一の恩返しだと思います。
2023年04月17日
何事も基礎が肝心?
Hi, everyone!What's new?
私的なことですが、スポーツジムで2年ほど前から、バレーのレッスンを始めました。大人になってから始めたバレー。見よう見まねで先生やバレー歴の長い人たちの姿を見ながら、やっているものの、なかなかハードルが高く大変です。そして、今日、先生に相談??してみたところ、今、私がとっているレッスンは、ある程度バレーをしてきた中級者対象ということで、その時間帯のまえに基礎レッスンがあるので、それにでてみたらどうかな、とアドバイスを受けました。確かにわからないままレッスンを受け続けるよりは、やはり基礎を身につけることが大事と思い、来週から、基礎レッスンにでてみようかと思っています。そのように考えると、語学でも同じことが言える?いま、受け持っている大学での英語のクラスもさまざまなレベルの学生たちがいます。そして、基礎がしっかりしていない学生たちは、いまひとつ伸び悩んでいるようです。授業では、まずは、しっかりとじっくりと基礎をおさえていくことが大切と思い、基礎力を身につける授業を心掛けるようにしています。バレーにしても語学にしても、まずは焦らず、基礎からと学ぶという姿勢が大事ではないかと感じています。

美しい姿を見せてくれる花々に感謝です!!
私的なことですが、スポーツジムで2年ほど前から、バレーのレッスンを始めました。大人になってから始めたバレー。見よう見まねで先生やバレー歴の長い人たちの姿を見ながら、やっているものの、なかなかハードルが高く大変です。そして、今日、先生に相談??してみたところ、今、私がとっているレッスンは、ある程度バレーをしてきた中級者対象ということで、その時間帯のまえに基礎レッスンがあるので、それにでてみたらどうかな、とアドバイスを受けました。確かにわからないままレッスンを受け続けるよりは、やはり基礎を身につけることが大事と思い、来週から、基礎レッスンにでてみようかと思っています。そのように考えると、語学でも同じことが言える?いま、受け持っている大学での英語のクラスもさまざまなレベルの学生たちがいます。そして、基礎がしっかりしていない学生たちは、いまひとつ伸び悩んでいるようです。授業では、まずは、しっかりとじっくりと基礎をおさえていくことが大切と思い、基礎力を身につける授業を心掛けるようにしています。バレーにしても語学にしても、まずは焦らず、基礎からと学ぶという姿勢が大事ではないかと感じています。

美しい姿を見せてくれる花々に感謝です!!
2023年04月16日
高齢者支援の難しさ
Hi, everyone! Did you have a good weekend?
先日、私の住む団地内の高齢者支援クラブでの定例会がありました。以前、ブログでもお話ししたように、大学のボラティアセンターの学生たちと団地の高齢者とどのように連携をとっていくのかという話し合いになったのですが、高齢者といっても元気で自分で生活できる高齢者と介護が必要な高齢者がいます。学生との触れ合い方においては、そのどちらにターゲットを絞るかによって、かかわり方も変わるということで、団地内の支援クラブの方向性を確認したところ、今、まさに介護や助けが必要な高齢者をまず考えていこう、という趣旨でした。しかし、私としては、元気な高齢者たちのことも視野に入れいくことも大切だと思います。元気な高齢者たちが、団地内の様々な活動に参加することによって、団地は活性化していくと考えられます。そして、それが、最終的には介護が必要な高齢者たちにもなんらかの形で良い影響を与えると思うのです。例えば、団地内での学生と共同のイベントを考えた場合、介護の必要な高齢者は、歩くのも大変で、そのようなイベントに行くこともできず、とても参加できないのではないか、という意見がでましたが、そのように考えてしまうと何もできません。今、元気な高齢者も数年後、あるいは、数十年後に介護が必要になる事は十分考えられます。少しでも心も体も元気に健康に過ごすためにも、学生からの違った視点、学生の持つ力はとても大きな意味をもたらすと思います。また、学生たちも高齢者たちと触れ合うことで、様々の違った見解に触れ、貴重な体験をすることができるはずです。この様に考えると、助けが必要な高齢者だけに絞らず、今はまだ元気な高齢者と両方を視野に入れていく方向性が求められているように感じました。そして、まずは、団地の支援クラブのメンバーに大学のボランティアセンターを知ってもらうことが不可欠と考え、情報共有ということでセンターから頂いた資料を回覧することにしました。これから、どのように進んて行くのか、はっきりしたものはまだ何も見えませんが、焦らず、時間がかかるのは覚悟でやっていきたいと思います。何もしなければ何も始まりませんものね。

新緑の季節になりました!!気持ちもさわやかにしてくれます。
先日、私の住む団地内の高齢者支援クラブでの定例会がありました。以前、ブログでもお話ししたように、大学のボラティアセンターの学生たちと団地の高齢者とどのように連携をとっていくのかという話し合いになったのですが、高齢者といっても元気で自分で生活できる高齢者と介護が必要な高齢者がいます。学生との触れ合い方においては、そのどちらにターゲットを絞るかによって、かかわり方も変わるということで、団地内の支援クラブの方向性を確認したところ、今、まさに介護や助けが必要な高齢者をまず考えていこう、という趣旨でした。しかし、私としては、元気な高齢者たちのことも視野に入れいくことも大切だと思います。元気な高齢者たちが、団地内の様々な活動に参加することによって、団地は活性化していくと考えられます。そして、それが、最終的には介護が必要な高齢者たちにもなんらかの形で良い影響を与えると思うのです。例えば、団地内での学生と共同のイベントを考えた場合、介護の必要な高齢者は、歩くのも大変で、そのようなイベントに行くこともできず、とても参加できないのではないか、という意見がでましたが、そのように考えてしまうと何もできません。今、元気な高齢者も数年後、あるいは、数十年後に介護が必要になる事は十分考えられます。少しでも心も体も元気に健康に過ごすためにも、学生からの違った視点、学生の持つ力はとても大きな意味をもたらすと思います。また、学生たちも高齢者たちと触れ合うことで、様々の違った見解に触れ、貴重な体験をすることができるはずです。この様に考えると、助けが必要な高齢者だけに絞らず、今はまだ元気な高齢者と両方を視野に入れていく方向性が求められているように感じました。そして、まずは、団地の支援クラブのメンバーに大学のボランティアセンターを知ってもらうことが不可欠と考え、情報共有ということでセンターから頂いた資料を回覧することにしました。これから、どのように進んて行くのか、はっきりしたものはまだ何も見えませんが、焦らず、時間がかかるのは覚悟でやっていきたいと思います。何もしなければ何も始まりませんものね。

新緑の季節になりました!!気持ちもさわやかにしてくれます。
2023年04月14日
人生を楽しむために働く?
Hi everyone!TGIF!(Thank God, it’s Friday!) Are you enjoying Friday night?
もうじき日本ではゴールデンウィークが始まりますね。もう、すでに予定を立てている方もいらっしゃるかもしれませんね。休みが来るたびに思うのは、ドイツの人々の長い休みにかける強い思いです。ドイツで生活を始めたときに、周りのドイツの友達の多くが、もうすでに翌年の旅のプランを立てているのにびっくりしました。早く計画を立てたほうが、きっとreasonableな値段で、希望のホテルがとれたり、良いサービスをget できるからでしょうか。とにかく気合が入っています。子どもたちも夏休みや冬休み以外にも2週間近く秋休みもあるなど学校の休みが長いので、それに合わせて一緒に休む親たちも多いです。私たちも冬にスキー旅行を計画したのですが、ホテル予約も大体が1週間単位で、日本でよくある1-2泊ほどの滞在予約できるホテルは、なかなか見つかりませんでした。ドイツの友達が言っていた言葉で今も思い出すのは、「遊ぶため、人生を楽しむために働くのだ」という言葉。つまり、働くのは、旅行など自分が楽しい時間を過ごすため、ということです。確かに私など、楽しいことが待っていると思うと仕事も頑張れるような気がします。もちろん、仕事自体を楽しめたら最高ですが。それほど、人生を楽しむという事はドイツの人たちにとって、とても大切なもののように思います。定年後になったらゆっくり楽しむというのもありますが、現役時代も人生を楽しむ、そんな生き方をドイツの友達から学んだような気がします。
もうじき日本ではゴールデンウィークが始まりますね。もう、すでに予定を立てている方もいらっしゃるかもしれませんね。休みが来るたびに思うのは、ドイツの人々の長い休みにかける強い思いです。ドイツで生活を始めたときに、周りのドイツの友達の多くが、もうすでに翌年の旅のプランを立てているのにびっくりしました。早く計画を立てたほうが、きっとreasonableな値段で、希望のホテルがとれたり、良いサービスをget できるからでしょうか。とにかく気合が入っています。子どもたちも夏休みや冬休み以外にも2週間近く秋休みもあるなど学校の休みが長いので、それに合わせて一緒に休む親たちも多いです。私たちも冬にスキー旅行を計画したのですが、ホテル予約も大体が1週間単位で、日本でよくある1-2泊ほどの滞在予約できるホテルは、なかなか見つかりませんでした。ドイツの友達が言っていた言葉で今も思い出すのは、「遊ぶため、人生を楽しむために働くのだ」という言葉。つまり、働くのは、旅行など自分が楽しい時間を過ごすため、ということです。確かに私など、楽しいことが待っていると思うと仕事も頑張れるような気がします。もちろん、仕事自体を楽しめたら最高ですが。それほど、人生を楽しむという事はドイツの人たちにとって、とても大切なもののように思います。定年後になったらゆっくり楽しむというのもありますが、現役時代も人生を楽しむ、そんな生き方をドイツの友達から学んだような気がします。
2023年04月12日
ボランティ活動を頑張る学生たちににエールを送る!
Hi, everyone! How are you doing?
昨日、今日と大学のボランティアセンターで担当の方々に現況を伺うことができました。それぞれの大学の学生たちが、被災地を含め、児童や高齢者、障害のある方たちなどのために様々なボランティア活動をおこなっているのを知り胸が熱くなりました。学生のボランティア活動は、被災地支援活動としてスタートしたものが多いということですが、今では、大学周辺の地域ボランティアや福祉ボランティアなどいろいろな活動に取り組んでいます。そして、学生のボランティア活動に対して、学生はクレディット、単位認定など考慮されるのかと聞くと、そのような制度はとくにないとのことでした。私が以前、ドイツのインターナショナルスクールで日本人コーディネーターとしてかかわっていた時、IB(International Baccalaureate)、国際バカロレアというプログラムを知りました。これは、大学入学資格になりますが、そのプログラムの中にCAS (Creativity, Activity, Service)というものがあり、ボランティア活動も含まれます。そして、この活動は高く評価されます。日本国内にも2021時点で167校ほど国際バカロレア認定校があるとされています。大学においてもボランティア活動は評価されても良いと思います。もちろん、単位や評価の為だけに活動するのは本末転倒ですが、熱心に活動に取り組む学生は、評価に値すると思います。今も頑張ってボランティア活動を続ける学生たちに、エールを送りたいと強く思いました。

ある大学のパンフから。素敵なフレーズですね!
昨日、今日と大学のボランティアセンターで担当の方々に現況を伺うことができました。それぞれの大学の学生たちが、被災地を含め、児童や高齢者、障害のある方たちなどのために様々なボランティア活動をおこなっているのを知り胸が熱くなりました。学生のボランティア活動は、被災地支援活動としてスタートしたものが多いということですが、今では、大学周辺の地域ボランティアや福祉ボランティアなどいろいろな活動に取り組んでいます。そして、学生のボランティア活動に対して、学生はクレディット、単位認定など考慮されるのかと聞くと、そのような制度はとくにないとのことでした。私が以前、ドイツのインターナショナルスクールで日本人コーディネーターとしてかかわっていた時、IB(International Baccalaureate)、国際バカロレアというプログラムを知りました。これは、大学入学資格になりますが、そのプログラムの中にCAS (Creativity, Activity, Service)というものがあり、ボランティア活動も含まれます。そして、この活動は高く評価されます。日本国内にも2021時点で167校ほど国際バカロレア認定校があるとされています。大学においてもボランティア活動は評価されても良いと思います。もちろん、単位や評価の為だけに活動するのは本末転倒ですが、熱心に活動に取り組む学生は、評価に値すると思います。今も頑張ってボランティア活動を続ける学生たちに、エールを送りたいと強く思いました。

ある大学のパンフから。素敵なフレーズですね!
タグ :ボランティア学生ボランティア活動
2023年04月10日
存在感のある人に!
Hi, everyone!How was your day?
4月になり、学校や職場などfreshmenたちが動き出しました。新たな年度のスタートを感じる時期ですね。私もいよいよ今週から授業が始まります。受け持つ履修生たちの名簿を眺めては、どんな学生たちが来るのか、とてもワクワクしています。そして、今日は家に帰る途中、赤や白のつつじの花が咲き始めているのを目にしました。花たちは、どんなことがあってもきちんと自分らしく、自分の存在を立派にしっかりと凛とした姿で私たちの前に姿を見せてくれます。花たちが、「見て、見て!私はここにいるよ!」とアピールしているようにみえ、なんだかほほえましく感じました。学生たちにも自分の意見をしっかり持ち、それを発信できるような存在感のある人になってほしいといつも思っています。海外にいると授業中でも友達と話しているときでも、黙っていて何も言わないでいると、何も意見がない、理解していない、話を聞いていない、ととられてしまうことが多々あります。アメリカの大学でも学生たちは、こんなこと質問するの、と思うような質問をしっかりと手を挙げてしていました。とにかく、自己表示が大切になってきます。私自身のクラスでも、受け身ではなく、だれもがさまざまな意見を出しやすいような環境づくり、そして、お互いの意見を否定することなく尊重し、皆で一緒に考えていけるようなクラスを心掛けたいと思います。今年も頑張ります!!
4月になり、学校や職場などfreshmenたちが動き出しました。新たな年度のスタートを感じる時期ですね。私もいよいよ今週から授業が始まります。受け持つ履修生たちの名簿を眺めては、どんな学生たちが来るのか、とてもワクワクしています。そして、今日は家に帰る途中、赤や白のつつじの花が咲き始めているのを目にしました。花たちは、どんなことがあってもきちんと自分らしく、自分の存在を立派にしっかりと凛とした姿で私たちの前に姿を見せてくれます。花たちが、「見て、見て!私はここにいるよ!」とアピールしているようにみえ、なんだかほほえましく感じました。学生たちにも自分の意見をしっかり持ち、それを発信できるような存在感のある人になってほしいといつも思っています。海外にいると授業中でも友達と話しているときでも、黙っていて何も言わないでいると、何も意見がない、理解していない、話を聞いていない、ととられてしまうことが多々あります。アメリカの大学でも学生たちは、こんなこと質問するの、と思うような質問をしっかりと手を挙げてしていました。とにかく、自己表示が大切になってきます。私自身のクラスでも、受け身ではなく、だれもがさまざまな意見を出しやすいような環境づくり、そして、お互いの意見を否定することなく尊重し、皆で一緒に考えていけるようなクラスを心掛けたいと思います。今年も頑張ります!!
2023年04月06日
「生きることなく、人生を終えたくない」
Hi, everyone! How are you doing?
今日は、前から見たいと思っていた「生きる Living」という映画を見ました。ノーベル賞作家のカズオ・イシグロが脚本を担当、そして黒澤明監督の「生きる」のリメイクということもあり、とても関心がありました。第2次世界大戦終結から数年後のロンドンを舞台にしたもので、お役所に勤める公務員の男性、ウィリアムズが主人公です。ある日、がんで余命が短いということを宣告され、人生を見つめ直し、生きるとは何かを問いかけていきます。そして、人生を見つめ直し、生まれ変わっていくのです。自分の中で答えを出した彼に、仕事への取り組み方、職場や他の人々とのつながり方一つをとっても、生命力がみなぎっていくのが伝わってきます。人は、何てこんなに生き生きと生きることができるのだろう。感銘しました。主人公がまるで別人のように変わっていくのをみながら、自分の中の気持ちもだんだんと熱くなってくるのを感じました。そして、ウィリアムズの言葉で一番記憶に残ったのは、「生きることなく、人生を終えたくない」というものです。この言葉は、とても深い意味を持っていると思います。「生きる」とは何か。「生きる」とは、ただ単に息をして体が生きているというだけではなく、もっと強いパワー、生命力、力強さを供え合わせているように思います。私も、ウイリアムズのように「生きる」とは何か、今一度しっかりと考え、これからの人生を「生きて」いこうと気持ちを新たにしました。

花びらが散った葉桜に生命力を感じます。
今日は、前から見たいと思っていた「生きる Living」という映画を見ました。ノーベル賞作家のカズオ・イシグロが脚本を担当、そして黒澤明監督の「生きる」のリメイクということもあり、とても関心がありました。第2次世界大戦終結から数年後のロンドンを舞台にしたもので、お役所に勤める公務員の男性、ウィリアムズが主人公です。ある日、がんで余命が短いということを宣告され、人生を見つめ直し、生きるとは何かを問いかけていきます。そして、人生を見つめ直し、生まれ変わっていくのです。自分の中で答えを出した彼に、仕事への取り組み方、職場や他の人々とのつながり方一つをとっても、生命力がみなぎっていくのが伝わってきます。人は、何てこんなに生き生きと生きることができるのだろう。感銘しました。主人公がまるで別人のように変わっていくのをみながら、自分の中の気持ちもだんだんと熱くなってくるのを感じました。そして、ウィリアムズの言葉で一番記憶に残ったのは、「生きることなく、人生を終えたくない」というものです。この言葉は、とても深い意味を持っていると思います。「生きる」とは何か。「生きる」とは、ただ単に息をして体が生きているというだけではなく、もっと強いパワー、生命力、力強さを供え合わせているように思います。私も、ウイリアムズのように「生きる」とは何か、今一度しっかりと考え、これからの人生を「生きて」いこうと気持ちを新たにしました。

花びらが散った葉桜に生命力を感じます。
2023年04月05日
Precious Moment!
Hi, everyone! What’s up?
ここ数日間で立て続けに人に会っています。数十年来の友だちだったり、大学の先輩だったり、大学の仕事仲間たち、そしてドイツから一時帰国している友だち。こんなに何人もの人たちに会って話すのは、本当に3年ぶりという感じで、対面でのコミュニケーションは、こんな感じだったんだと懐かしく思い出しています。コロナ禍はなかなか簡単に会えず、しかも会ったとしてもせいぜい1対1。今日のお昼は8人の仲間、そして夜は3人の友だちと食事を共にしました。なんといっても会話のやり取りがポンポンと行ったり来たり、キャッチボールをしているような感覚がとても新鮮でした。そして、マスクをとった顔にみる表情もコミュニケーションにとってとても大きな要素をしめていることを実感しました。話が弾んだ後は、なんだか今までたまっていたものをすべて吐き出したようなすっきり感、爽快感、暖かな気持ち、人のぬくもり、いろいろな感情が押し寄せてきました。そして、別れる時は、思わずhug! オンラインやSNSでは感じることのできないほんわかとした人のあたたかな体温、ぬくもりを感じることができました。もちろん、コロナ前でも人に会うことにより楽しい時間を共有したという気持ちはありましたが、人との触れあい、暖かさをこんなにしっかり感じることはなかったような気がします。これからも対面でのコミュニケーション、人との繋がりを今以上に大切にしていきたいと強く思いました。まさにprecious moment!

まさに自然界のprecious momentです! (sunset)
ここ数日間で立て続けに人に会っています。数十年来の友だちだったり、大学の先輩だったり、大学の仕事仲間たち、そしてドイツから一時帰国している友だち。こんなに何人もの人たちに会って話すのは、本当に3年ぶりという感じで、対面でのコミュニケーションは、こんな感じだったんだと懐かしく思い出しています。コロナ禍はなかなか簡単に会えず、しかも会ったとしてもせいぜい1対1。今日のお昼は8人の仲間、そして夜は3人の友だちと食事を共にしました。なんといっても会話のやり取りがポンポンと行ったり来たり、キャッチボールをしているような感覚がとても新鮮でした。そして、マスクをとった顔にみる表情もコミュニケーションにとってとても大きな要素をしめていることを実感しました。話が弾んだ後は、なんだか今までたまっていたものをすべて吐き出したようなすっきり感、爽快感、暖かな気持ち、人のぬくもり、いろいろな感情が押し寄せてきました。そして、別れる時は、思わずhug! オンラインやSNSでは感じることのできないほんわかとした人のあたたかな体温、ぬくもりを感じることができました。もちろん、コロナ前でも人に会うことにより楽しい時間を共有したという気持ちはありましたが、人との触れあい、暖かさをこんなにしっかり感じることはなかったような気がします。これからも対面でのコミュニケーション、人との繋がりを今以上に大切にしていきたいと強く思いました。まさにprecious moment!

まさに自然界のprecious momentです! (sunset)
タグ :対面でのコミュニケーション繋がり
2023年04月02日
gymとの向き合い方
Hi, everyone! Did you have a relaxing weekend?
今、大学の春休み中なので、比較的時間にゆとりがあり、gym に週3~4回ぐらいのペースで行っています。さらに時間が許せば、1日に2コースのレッスンをとったりすることもあります。gymにほぼ毎日来ている人や月8回のコースで来ている人、そしてgymのサウナやお風呂が目的で来る人など様々なようです。さて、自分がなぜ、gymに行くのか、少し考えてみました。自分にとってはまずは、スポーツをした後のすっきり感がたまらないからです。ドイツに行っているときは、gymに行っていなかったので、気分的にもなんだかすっきりせず、もやもやすることもありました。帰国した翌日にすぐにgymに行って汗をながした時の快感。最高でした!!そして、やはりもう一つの理由は、健康に良い、ということです。ほかに、これは理由というわけではありませんが、少しずつ、知り合いも増え、一言二言ちょっとした会話も楽しめるようにもなったのも嬉しいです。ただ、頻繁に行くようになると、なんとなく義務感のようなものが芽生えてきました。「行かなければいけない」という気持ち。もちろん、運動不足解消のためには良いと思いますが、義務感からでは、心底楽しめないような気もします。先日、結構疲れていたのですが、「義務感?」のようなものが頭をもたげ、無理して?行ったのですが、体も心もいつもの爽快感を味わうことができませんでした。教訓として、体も疲れているときは、無理せず、休むという事。もちろん、怠けてばかりではいけないと思うのですが、そのあたりのバランスが難しいと最近感じています。そんななか、先日、ドイツで週4回ほどテニスをしている日本人の友達に、ドイツ人のスポーツとの向き合い方を聞いてみました。答えは「とにかく楽しむ」だそうです。その友達は、日本人のグループとドイツ人グループ両方のクラブでテニスプレイをしていて、時々それぞれのグループとも仲間同士で試合をするそうです。そんな時、日本の人は結構真剣な人が多いのに対し、ドイツ人グループは、リラックスして試合を楽しんでいるそうです。そして試合が終わってから、ビールを飲んでみんなでワイワイ!私も楽しみながら、スポーツやgymと長くつきあっていきたいと思います。

花屋さんで個性的な花を見つけました。「ラナンキュラス」という名前だそうです。ストックとの組み合わせ、なかなか素敵で気に入っています!
今、大学の春休み中なので、比較的時間にゆとりがあり、gym に週3~4回ぐらいのペースで行っています。さらに時間が許せば、1日に2コースのレッスンをとったりすることもあります。gymにほぼ毎日来ている人や月8回のコースで来ている人、そしてgymのサウナやお風呂が目的で来る人など様々なようです。さて、自分がなぜ、gymに行くのか、少し考えてみました。自分にとってはまずは、スポーツをした後のすっきり感がたまらないからです。ドイツに行っているときは、gymに行っていなかったので、気分的にもなんだかすっきりせず、もやもやすることもありました。帰国した翌日にすぐにgymに行って汗をながした時の快感。最高でした!!そして、やはりもう一つの理由は、健康に良い、ということです。ほかに、これは理由というわけではありませんが、少しずつ、知り合いも増え、一言二言ちょっとした会話も楽しめるようにもなったのも嬉しいです。ただ、頻繁に行くようになると、なんとなく義務感のようなものが芽生えてきました。「行かなければいけない」という気持ち。もちろん、運動不足解消のためには良いと思いますが、義務感からでは、心底楽しめないような気もします。先日、結構疲れていたのですが、「義務感?」のようなものが頭をもたげ、無理して?行ったのですが、体も心もいつもの爽快感を味わうことができませんでした。教訓として、体も疲れているときは、無理せず、休むという事。もちろん、怠けてばかりではいけないと思うのですが、そのあたりのバランスが難しいと最近感じています。そんななか、先日、ドイツで週4回ほどテニスをしている日本人の友達に、ドイツ人のスポーツとの向き合い方を聞いてみました。答えは「とにかく楽しむ」だそうです。その友達は、日本人のグループとドイツ人グループ両方のクラブでテニスプレイをしていて、時々それぞれのグループとも仲間同士で試合をするそうです。そんな時、日本の人は結構真剣な人が多いのに対し、ドイツ人グループは、リラックスして試合を楽しんでいるそうです。そして試合が終わってから、ビールを飲んでみんなでワイワイ!私も楽しみながら、スポーツやgymと長くつきあっていきたいと思います。

花屋さんで個性的な花を見つけました。「ラナンキュラス」という名前だそうです。ストックとの組み合わせ、なかなか素敵で気に入っています!