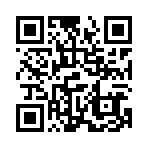2023年08月30日
セミナーに参加して
今日は、大学主催の”English Communication Strategies”のセミナーに1日参加しました。これは、実際に大学で教育に携わる先生のための研修セミナーです。毎年、夏にあるのですが、今回初めて参加してみました。今回参加してみて、改めて、じっくりと英語によるコミュニケーション法について見直すことができ、大変良かったと思っています。そして、講師の方からの学びに加えて、参加なさったそれぞれ専門や研究分野の違う先生方が、学生との英語によるコミュニケーションにおいて、どのような工夫をし、また、どのような難しさに直面しているのかも知ることができ、大変参考になりました。教育に携わる者として、自分のやりかただけに固守するのではなく、研修会に参加したり、他の先生方の意見を聞いたり、外部からの新鮮な風を入れることが大事だと思いました。そして同時に、このようなコミュニケーション法を知ることは有意義ですが、まずは学生たちの興味ややる気を引き出すこと、そして英語を使うことへの抵抗感をなくすことが重要で、そして何よりも英語によるコミュニケーションの楽しさ、広がる可能性について伝えていきたいと感じました。9月から始まる後期の授業、気持ちも新たにして学生たちと向き合っていこうと思っています。

南アフリカの旅で大好きになった花 "a flower of paradise"「極楽鳥花」色鮮やかでとても素敵な花です。

南アフリカの旅で大好きになった花 "a flower of paradise"「極楽鳥花」色鮮やかでとても素敵な花です。
2023年08月28日
人間と自然の共存
今日は、お墓参りに行ってきました。お墓参りの時に、ふと空を見上げると夏の入道雲と秋のすじ雲が融合しているように見ました。そして帰り道、セミの鳴き声とともに秋の虫の鳴き声が融合。着実に秋の気配が少しづづ感じられるようになってきたのではないでしょうか。夏に南アフリカで野生の動物たちと出会ってから、人間は自然界の一部、そして人間と自然は共存しているという気持ちを強くしました。そんな中で今日読んだ新聞の記事で、米国ニューヨーク在住のインド人作家、アミタヴ・ゴーシュ氏が述べた文面が目に留まりました。彼は、近代化についてこう述べています。
「近代化」が「人間と自然を切り離した」「(我々は)近代以前の世界にあった、人間を自然の一部と捉える思考を取り戻すべきなのです」
まさに同感です。さらに、記事には、インド建国の父ガンジ―の言葉も引用されていました。
「私は人間だけではなく、全ての生命と一体になりたい。地上を這う存在とも一体になりたい。‥‥全ての生命は、それがどんな形態であろうとも本質的にはひとつなのです」
とても強く心に響くメッセージだと思います。そして、アミタヴ氏は、「(作家の私は)人間以外の声にも耳を澄ませ、伝える責務」があると結んでいました。彼の述べる自然と向き合う姿勢は、わたしたちすべての人にも言えるのではないでしょうか。自然が伝えるメッセージに素直に謙虚に耳を傾ける必要があるように思います。夏から秋への移り変わり、自然はいろいろな形、姿を通して、私たちにメッセージを送っています。それらを慈しみ、大切にしていきたいという気持ちを新たにしました。

インド洋の海岸でみた美しい砂紋‼自然の織り成す美しさに感銘しました。
「近代化」が「人間と自然を切り離した」「(我々は)近代以前の世界にあった、人間を自然の一部と捉える思考を取り戻すべきなのです」
まさに同感です。さらに、記事には、インド建国の父ガンジ―の言葉も引用されていました。
「私は人間だけではなく、全ての生命と一体になりたい。地上を這う存在とも一体になりたい。‥‥全ての生命は、それがどんな形態であろうとも本質的にはひとつなのです」
とても強く心に響くメッセージだと思います。そして、アミタヴ氏は、「(作家の私は)人間以外の声にも耳を澄ませ、伝える責務」があると結んでいました。彼の述べる自然と向き合う姿勢は、わたしたちすべての人にも言えるのではないでしょうか。自然が伝えるメッセージに素直に謙虚に耳を傾ける必要があるように思います。夏から秋への移り変わり、自然はいろいろな形、姿を通して、私たちにメッセージを送っています。それらを慈しみ、大切にしていきたいという気持ちを新たにしました。

インド洋の海岸でみた美しい砂紋‼自然の織り成す美しさに感銘しました。
Posted by ゆっこ at
00:14
│Comments(0)
2023年08月25日
旅の持つ意味:日常生活と非日常の世界
ドイツ・アフリカの旅を終えて今、思う事!それは旅のもつ醍醐味です。毎日のルーティンから離れ、非日常に身を置くこと、そこには新たな発見や気づきがあります。もちろん、おいしい食事や美しい風景もさることながら、旅先での人々との出会い、数えきれないほどの発見があるはずです。旅は、わたしたちに多くのパワー、エネルギをチャージしてくれるように思います。まさに非日常の世界との出会いと言えるのではないでしょうか。さらに、旅のあと日常生活に戻った時にも今までの生活がとても新鮮に感じらるという効果もあるように思います。実は、今日は1日中、大学主催の英文アカデミック・ライティングのセミナーにオンラインに参加したのですが、じっくりとセミナーに参加することに多くの喜び、充実感を感じました。大学が夏休みになり、しばらく、大学の授業から離れていたこともあるでしょう。でもこれは旅に出たことによる効果だと思います。このように、旅を私たちを非日常の世界に連れて行ってくれると同時に旅の後の日常生活にも新鮮な気持ちを送り込んでくれます。onとoffの相乗効果ともいえるのでは。ただ、運動に関してはいささか疑問です。昨日久しぶりにジムに行ったら、今日は、筋肉痛がひどく大変でした! 旅に行っているときも少しだけでありますが、自主トレをしていたつもりだったのですが・・・・こればっかりは、できるだけ毎日続けることなのでしょうか‽?これからも上手に旅を人生の中に取り入れ、日常と非日常世界を共に楽しみたいと思います。

大きなサイたちが目の前をのそのそと通り過ぎていく。私にとってはまさに非日常の世界でした!

大きなサイたちが目の前をのそのそと通り過ぎていく。私にとってはまさに非日常の世界でした!
2023年08月24日
コミュニケーションの楽しさ!
日本に帰国して2日たち、一番思い出になったのは、人とのつながり、そして楽しいコミュニケーションができたことです。今回のドイツ・アフリカ滞在では、実に多くの人と出会い、楽しい時間を持つことができました。日本に帰り、それが減ってしまい、寂しい限りです。コミュニケーションといっても言葉だけではありません。目と目があえば、にっこり、そしてCaféでもパン屋さんでもレストランでも至るところで”Hello!" ”Good morning!” そして””Einen Schönen Tag!"など様々なあいさつの言葉を交わします。日本でも「こんにちは」とお店に入ると言われることもありますが、目と目が合ってにっこり!という雰囲気ではないような??この癖がついて、今日、近くに買い物に行くとき、通りすがりの知らない人に「にっこり」したら、怖がられました(笑)もちろん、旅先で知り合った人や友達との会話もとても弾みました。アフリカの旅では、アフリカの現地の方たち以外に、イスラエル人、オランダ人、英国人、ドイツ人などさまざまの国籍の人たちが観光に来ているので、彼らと出会うことがありました。共通語は英語!特にサファリgame reserveでは現地のアフリカ人のレンジャーさんとのランチや、最後の夜は、皆で薪を囲んでお話をしながらの夕食もありました。皆で、旅の思い出やそれぞれの違った文化や考え方の話をしたり…かなり盛り上がりました。その時感じたことは、海外に旅に出たら、是非、現地の日本語でない英語のツアーに参加することをお勧めします。そうすれば、いろいろな国から来ている人たちとの出会いがあり、話も弾むはずです。そして、もちろん、言葉は、できたほうが楽しいですね。でも流ちょうに話さなければ、と構える必要はありません。イスラエル人家族のご主人も一生懸命に英語を話していました。奥さんのサポ―トを受けながら(笑)。相手への思いやり、相手のことをよく知ろうという好奇心があれば、必ず心が通じると思います。次の旅が楽しみです!

南アフリカの滞在先でみたインド洋のsun riseです。

南アフリカの滞在先でみたインド洋のsun riseです。
2023年08月21日
ドイツのパン
南アフリカからドイツに戻り、数日になりますが、とてもうれしいのは、おいしいドイツのパンを楽しめることです。ドイツのパンは、大変種類が多く、中でも私は、ライ麦粉を使った黒パンが大好きです。日本の白い柔らかいパンと違い、色は黒めになります。黒パンは、大きめのパンで、ライ麦の含有量により、黒さと柔らかさが違います。ライ麦の含有量が多くサワー種が使われると少し酸味があり、歯ごたえもあります。ドイツのパン屋さんでは、お願いすると、大きなパンを希望の厚さにスライスしてくれますが、先日、行ったスーパーでは、自分でパンをスライスする機械が設置されていました。また、ドイツの人は黒パンが大好きなようでよく黒パンを使ったメニューを見かけます。今日は、黒パンの上に卵料理やルッコラ、生ハムなどを載せた料理をいただきました。また、黒パンにカマンベールやクリームチーズをのせてもとてもおいしいです。日本でもドイツのパンを見かけることが多くなってきていますが、もっとたくさんの種類の大型パンが出回り、手ごろな値段で買えたらいいなと思います。


2023年08月17日
I'll miss my job and nature!
Air Link というかわいい鳥のマークのアフリカ国内線でヨハネスブルグまで移動し、そこから約11時間かけてドイツに戻ってきました。今回の南アフリカ旅行で感じたことは、人びとのもつ強い家族愛です。旅行中のサファリツアーで3日間常に同行してくれたレンジャー、Trustさん。Trustさんは、この仕事につきもう20年とのことでした。自分は自然が大好きだし、人との触れ合いもありとても楽しいが、家族になかなか会えないのがつらい、と言っていました。確かにサファリゲームドライブは、早朝6時半から9時半までのモーニングサファリ、夕方3時半から6時半ごろまでの夕方サファリ、そして夜は、ゲストと一緒に食事をすることもあります。夜遅く、朝早いので、家に帰る時間はなく、ゲストと同じロッジにstayしているとのこと。そのため、家族と会う時間はとても少なく、週7時間ほどしか7歳の息子さんに会えないそうです。大好きな仕事と家族に会う時間の少なさにジレンマを感じ、なんと、今年でこの仕事を辞め、モザンビークにいる自分の家族のところに戻るということでした。彼にとっては、家族との時間をもっと大切にしたいという強い気持ちがその決断をもたらしたようです。”I'll miss my job and nature!"と言った時、Trustさんは少し涙ぐんでいるようでした。また、サファリツアーでずっと一緒だったイスラエル人の家族は、2人のお嬢さんたちを連れての旅行でした。そして「私たちにとって家族は一番!だから、いつでも一緒に旅行するんです。」と話していました。家族に対する思い、全ての人々が強くいいだいているんだなあと実感しました。


2023年08月15日
野生動物がつなぐ人間社会

今日は、サファリロッジ滞在の最後の夜。ボマディナーでもてなしてくれました。ボマディナーとは、南アフリカのサファリロッジでよくみられ、キャンプファイヤーのようなものです。薪の周りに宿泊客が皆集まり、楽しく、おしゃべりをしながら、南アフリカの薪で焼いたお肉を楽しみます。もちろん、南アフリカのワインやサラダ、パン、デザートも。そして、サプライズとして、レンジャーやホテルスタッフによる踊りと歌のパフォーマンスがあり、その声量とリズミカルな動きに皆びっくり‼️
ボマディナーでの集いも含めて、早朝と夕方のゲームサファリを通して皆が、うちとけ、優しい気持ちになります。
今回の滞在は、野生動物の持つ生命力、賢さや知恵に感銘しただけでなく、かれらには私たち人間を人種や宗教に関係なく結びつけるパワーがあることを感じさせてくれました。
Posted by ゆっこ at
07:18
│Comments(0)
2023年08月14日
ゲームサファリにみる神聖な自然界!
早朝、5:30に起きてから、軽くコーヒーとマフィンを食べ、6:30から早朝サファリに出発。子ども3匹を連れたお母さんライオンを発見。子どもたちがしっかりついて来ているか確認しながら移動する姿に、母親の愛情を感じました。9:30頃ロッジにもどり、朝食。その後、ロッジでのんびりすごし、遅いお昼を食べ、3:30から、Evening サファリへ。群れをなす家族象たちが次から次へと草むらの間から、音を立てながら近づいてきました。興奮冷めやらず。レンジャーは、冷静そのもの。
大きな声を出さず、ジープに座っているように指示をうけました。すると象たちはゆっさゆっさと体をゆらしながら、通り過ぎていきました。自然界のなかで動物達をこんなに近くにみることははじめてで自然界の素晴らしさを感じると同時にとても神聖な気持ちになりました。

大きな声を出さず、ジープに座っているように指示をうけました。すると象たちはゆっさゆっさと体をゆらしながら、通り過ぎていきました。自然界のなかで動物達をこんなに近くにみることははじめてで自然界の素晴らしさを感じると同時にとても神聖な気持ちになりました。
Posted by ゆっこ at
05:39
│Comments(0)
2023年08月13日
2023年08月13日
南アフリカGame reserve
今日game reserve へ。ここは、野生の動物たちを守るための保護地区で、ジープでフィールをレンジャーとともに駆け巡りました。途中、巨大な象が間近まで迫り、すごい迫力でした。シマウマやインパラたちも発見。大自然を肌で感じ、野生の動物たちをとても身近に感じることができました。レンジャーから、動物たちをrespectすることの大切さを学びました!
Posted by ゆっこ at
05:43
│Comments(0)
2023年08月12日
インド洋海岸白い砂浜の風紋!

今日は、プレッテンバーグベイで、Whale watching をしました。大きな鯨を目の当たりにして、あまりの迫力にびっくり。午後は、町の近くの国立公園へ。手つかずの自然が残り、インド洋の海岸沿いの砂浜に幾何学模様のような風紋を見つけ、その美しさに感銘。このような自然保護区がたくさん残されることを願わずにはいられませんでした。
Posted by ゆっこ at
04:08
│Comments(0)
2023年08月11日
絶景ガーデン•ルート!

Hi, everyone! What’s up?
今日は、ケープタウンからガーデンルートを7時間のほど走り、インド洋に面した美しい町プレッテンバーグベイに来ています。途中、山脈を背景に花が咲き乱れる草原、フルーツ畑、羊や牛が放牧されている牧草地、そして小川や湖、渓谷、さらには木々が鬱蒼と生い茂るジャングルなどさまざまな自然環境を楽しめました。なかでも延々と続く菜の花畑がまるで黄色の絵の具で絵を描いたように美しく、魅了されました。このルートには、多くのリゾート地が点在し、シーズン中は大変混み合うとのこと。いまは、冬なので静か。オフシーズンに来て、潮騒の音を聞きながら、のんびりと過ごすのも一つの楽しみ方だと思いました。
2023年08月10日
オー・サミ・スィ・ウィンケル1904 年からのお店
Hi, everyone ! How are you doing?
今日は、ワインランド巡りの拠点となる町、ステレンボッシュを散策。南アフリカでケープタウンに次いで2番目に古い町。楽しかったのは、1904 年からあるお店で、だちょうの卵から、昔からのお菓子やジャム、干し魚、古本などさまざまななものが売られていました。ふと、小さい時によく行った駄菓子屋を思い出し、ノスタルジックな気分になりました。また、たいへん興味深かったのは、17-19世紀の家を4軒、移築復元した博物館です。当時の服装をしたガイドさんたちが、詳しく説明してくれました。ケープダッチから、ジョージ、ビクトリア時代の各時代の様式が手に取るようにわかり、とても良かったです。また、フランスから逃れてきた新教徒たちが開いた町もあり、そこはフランスの名前がたくさん残り、フランス風の料理を出すお店も多いとのこと。各町が、さまざまな歴史を持ち、とても印象的でした。

今日は、ワインランド巡りの拠点となる町、ステレンボッシュを散策。南アフリカでケープタウンに次いで2番目に古い町。楽しかったのは、1904 年からあるお店で、だちょうの卵から、昔からのお菓子やジャム、干し魚、古本などさまざまななものが売られていました。ふと、小さい時によく行った駄菓子屋を思い出し、ノスタルジックな気分になりました。また、たいへん興味深かったのは、17-19世紀の家を4軒、移築復元した博物館です。当時の服装をしたガイドさんたちが、詳しく説明してくれました。ケープダッチから、ジョージ、ビクトリア時代の各時代の様式が手に取るようにわかり、とても良かったです。また、フランスから逃れてきた新教徒たちが開いた町もあり、そこはフランスの名前がたくさん残り、フランス風の料理を出すお店も多いとのこと。各町が、さまざまな歴史を持ち、とても印象的でした。

2023年08月09日
南アフリカとワイン
Hi,everyone! How are you doing?
ケープタウンの街から、車で40分ほどかけて南アフリカワインの生産地、ワインランドにやってきました。南アフリカのワインは.オランダ東インド会社のケープ補給基地の初代総督であったファンリーベックが、ブドウの苗木を植えたことから、ワイン造りが始まったとのこと。約350年もの歴史があることにびっくり。このワインランドには、多くのワイナリーがあり、ワインの試飲だけでなく、美しい庭園、周りの岩山の風景、さらには、ビクトリア時代の建物やケープダッチ様式の建物など、ワインと一緒に自然と歴史を楽しむことができます。近くの街にはワインを研究する大学もあるそうで、南アフリカがワイン造りにとても力を注いでいるのが見えます。南アフリカワインの一つ、ピノタージュは、その大学の教授により、他のワインとの交配種から選抜されたとこと。ワインと食事を楽しみながら、自然を体に感じ、歴史に思いを馳せる。とても素敵な時間だと思いました。

ケープタウンの街から、車で40分ほどかけて南アフリカワインの生産地、ワインランドにやってきました。南アフリカのワインは.オランダ東インド会社のケープ補給基地の初代総督であったファンリーベックが、ブドウの苗木を植えたことから、ワイン造りが始まったとのこと。約350年もの歴史があることにびっくり。このワインランドには、多くのワイナリーがあり、ワインの試飲だけでなく、美しい庭園、周りの岩山の風景、さらには、ビクトリア時代の建物やケープダッチ様式の建物など、ワインと一緒に自然と歴史を楽しむことができます。近くの街にはワインを研究する大学もあるそうで、南アフリカがワイン造りにとても力を注いでいるのが見えます。南アフリカワインの一つ、ピノタージュは、その大学の教授により、他のワインとの交配種から選抜されたとこと。ワインと食事を楽しみながら、自然を体に感じ、歴史に思いを馳せる。とても素敵な時間だと思いました。

2023年08月08日
南アフリカ国花プロテアに魅了される
Hi,everyone! What’s up?
今日は、世界遺産に登録されたケープ植物区保護地域群にある植物園へ。約2万2,000種類ある南アフリカの植物のうち、9,000種類がここで栽培、研究されているそうです。園内には、小川や木の橋がかかり、遊歩道が整備されていました。そして素晴らしいと思ったのは、視覚に障害のある人も困らないように説明や方向をあらわすボードに点字があることです。全ての人が皆平等に植物園を楽しめるようにという思いが伝わってきました。たくさんある植物の中で、目を引いたのは、南アフリカの国花のキングプロテアです。なんと直径20cmほどの巨大な花でした。アロエの花も初めて見ることが出来ました。300種類もあるアロエのほとんどは南アフリカ産とのこと。他にも、花が針刺しのようになっていることから、ピンクッションと呼ばれている花、さまざまな色合のエリカの花も堪能しました。現地のガイドさんによるとこの植物園を訪れた後、美しい植物たちに刺激をうけ、花々の愛好家になる人も多いとのこと。納得です!たくさんの花々に会えてとても幸せな気分になりました。

今日は、世界遺産に登録されたケープ植物区保護地域群にある植物園へ。約2万2,000種類ある南アフリカの植物のうち、9,000種類がここで栽培、研究されているそうです。園内には、小川や木の橋がかかり、遊歩道が整備されていました。そして素晴らしいと思ったのは、視覚に障害のある人も困らないように説明や方向をあらわすボードに点字があることです。全ての人が皆平等に植物園を楽しめるようにという思いが伝わってきました。たくさんある植物の中で、目を引いたのは、南アフリカの国花のキングプロテアです。なんと直径20cmほどの巨大な花でした。アロエの花も初めて見ることが出来ました。300種類もあるアロエのほとんどは南アフリカ産とのこと。他にも、花が針刺しのようになっていることから、ピンクッションと呼ばれている花、さまざまな色合のエリカの花も堪能しました。現地のガイドさんによるとこの植物園を訪れた後、美しい植物たちに刺激をうけ、花々の愛好家になる人も多いとのこと。納得です!たくさんの花々に会えてとても幸せな気分になりました。

2023年08月07日
アフリカの風!

Hi, everyone? What’s new?
ドイツのフランクフルトから、フライト11時間15分ほどかけて、南アフリカケープタウンにやってきました。こちらは、今、冬で日中温度は18度ぐらいで少し肌寒いです。今日は、ずっと行きたかった喜望峰までドライブしました。インド洋と大西洋が交わるケープ半島の最南端。そこには波しぶきをあげた荒々しい海の姿。あまりの雄大な自然を前に気持ちまで解放されるようでした。街並みは、ヨーロッパの都市のようでアフリカにいるような気がしません。でも、喜望峰にある自然保護区では、大きなダチョウたちやバブーン(ヒヒ)、体調が2mもあるようなアンテロープたちを目の当たりにして、やはり、ここはアフリカなんだ、と実感しました!レストランでは、ワニのステーキを初めてトライ!滞在中は、思いっきり、南アフリカの風そして空気を感じていきたいと思っています。
2023年08月06日
おもてなしを見習う!
Hi, everyone! How are you doing?
先日、ドイツ滞在中にお世話になったドイツ人宅にお茶に招待されて、お邪魔しました。ご家族の方たちもいらして、カフェで会うのと違い、アットホームな和やかな雰囲気のなかでなんと4時間近くもお話し。ご主人は、定年後、ご自分のお庭でトマト、ズッキーニ、ナシ、リンゴなどを育てたり、ばら、アジサイなど美しい花々も丁寧に育てていました。なかでも、ジャガイモストーリーというのがあって、水やりがうまくいかず、とっても小さなジャガイモしかできなかったと楽しそうにお話ししていました。そして、帰り際に突然、ご主人の姿が見えなくなったと思ったら、ご自分のお庭のバラの花と、なし、トマト、ズッキーニをとってきて、どうぞ、と一言。心のこもったおもてなしに感激しました。今回の訪問はみながうちとけ、とても楽しく、話が弾んだことから、私もこれからは、こんな素敵なおもてなしができたらいいなと思いました。

先日、ドイツ滞在中にお世話になったドイツ人宅にお茶に招待されて、お邪魔しました。ご家族の方たちもいらして、カフェで会うのと違い、アットホームな和やかな雰囲気のなかでなんと4時間近くもお話し。ご主人は、定年後、ご自分のお庭でトマト、ズッキーニ、ナシ、リンゴなどを育てたり、ばら、アジサイなど美しい花々も丁寧に育てていました。なかでも、ジャガイモストーリーというのがあって、水やりがうまくいかず、とっても小さなジャガイモしかできなかったと楽しそうにお話ししていました。そして、帰り際に突然、ご主人の姿が見えなくなったと思ったら、ご自分のお庭のバラの花と、なし、トマト、ズッキーニをとってきて、どうぞ、と一言。心のこもったおもてなしに感激しました。今回の訪問はみながうちとけ、とても楽しく、話が弾んだことから、私もこれからは、こんな素敵なおもてなしができたらいいなと思いました。

2023年08月04日
K20での気づき
Hi, everyone! How are you doing?
昨日、今いるドイツの町の美術館、K20に行ってきました。この美術館はこじんまりとした市の美術館ですが、ピカソ、セザンヌ、クレー、ダリなど近現代アートが常設展示されています。半年ぶりに行ったのですが、その時に感じたことがあります。それは、館内の監視が前より厳しくなったことです。以前は、作品にかなり近づいても作品に触れなければ大丈夫でしたが、昨日は作品から約1メートルほど離れて鑑賞するようにと言われました。さらに、館内が少し暑かったので、上着を脱いで手に持っていたら、監視員に「腰に巻くか、肩にかけてください」と注意を受けました。最近行った上野の美術館では、上着を手にもったまま鑑賞していたような気がしますが。また、監視員の人数も心持ち、増えたようにみえました。これはもしかして、最近あった環境活動家たちが絵画を標的にした事件に関係しているのかと思いました。実際、ドイツの美術館にある絵画も被害にあっています。昨今、地球の温暖化や異常気象、懸念される世界情勢などが取りあげられていますが、美術館についてもこれから自由きままに作品を鑑賞できなくなってしまうのか、と考えると寂しい気持ちになりました。

K20の展示作品の一つです。
昨日、今いるドイツの町の美術館、K20に行ってきました。この美術館はこじんまりとした市の美術館ですが、ピカソ、セザンヌ、クレー、ダリなど近現代アートが常設展示されています。半年ぶりに行ったのですが、その時に感じたことがあります。それは、館内の監視が前より厳しくなったことです。以前は、作品にかなり近づいても作品に触れなければ大丈夫でしたが、昨日は作品から約1メートルほど離れて鑑賞するようにと言われました。さらに、館内が少し暑かったので、上着を脱いで手に持っていたら、監視員に「腰に巻くか、肩にかけてください」と注意を受けました。最近行った上野の美術館では、上着を手にもったまま鑑賞していたような気がしますが。また、監視員の人数も心持ち、増えたようにみえました。これはもしかして、最近あった環境活動家たちが絵画を標的にした事件に関係しているのかと思いました。実際、ドイツの美術館にある絵画も被害にあっています。昨今、地球の温暖化や異常気象、懸念される世界情勢などが取りあげられていますが、美術館についてもこれから自由きままに作品を鑑賞できなくなってしまうのか、と考えると寂しい気持ちになりました。

K20の展示作品の一つです。
2023年08月02日
恋しい日本の夏?
Hi everyone! What's new?
半年ぶりにドイツにやってきました。日中気温18度ぐらいでなんと日本との温度差が20度近く。あまりの温度差に体もびっくりしているようです。早速、涼しい場所ならでは、とライン川河畔に散歩に出かけました。河畔にはたくさんの羊たちがのんびりと草を食べていました。そして橋を渡り、市の中心街へ行き、お気に入りのカフェで一息。それにしてあまりの涼しさで夏が終わり、一気に秋になってしまったようで、セミがにぎやかに鳴く日本のあの暑い夏がちょっぴり恋しくなりました。何事もないものねだりですね。さらには、家の近くの池から聞こえるウシガエルの鳴き声までもなつかしく・・・・・教訓!!今いるまさに今の状況を心おきなくたのしむこと!大切だと思いました。

半年ぶりにドイツにやってきました。日中気温18度ぐらいでなんと日本との温度差が20度近く。あまりの温度差に体もびっくりしているようです。早速、涼しい場所ならでは、とライン川河畔に散歩に出かけました。河畔にはたくさんの羊たちがのんびりと草を食べていました。そして橋を渡り、市の中心街へ行き、お気に入りのカフェで一息。それにしてあまりの涼しさで夏が終わり、一気に秋になってしまったようで、セミがにぎやかに鳴く日本のあの暑い夏がちょっぴり恋しくなりました。何事もないものねだりですね。さらには、家の近くの池から聞こえるウシガエルの鳴き声までもなつかしく・・・・・教訓!!今いるまさに今の状況を心おきなくたのしむこと!大切だと思いました。