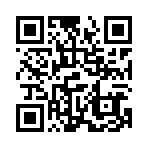2023年09月28日
牧野標本館を訪ねて
今日は、前から訪れたかった都立大学の「牧野標本館」に足を運んでみました。そこには、牧野富太郎が残した標本の一部やシーボルトが来日した際に集めた標本の一部などが展示されていました。牧野氏が、なんと60年以上にわたって、同じ場所で同じ植物種の標本を採集したと知り、植物に対する熱い気持ちが伝わってきました。まるで自分の子どもや孫の成長をいつくしむように一瞬、一瞬に見せる姿や形を見逃さないようにという思い。素晴らしいです!そのpassionは、彼が90歳ごろ、自宅で書した「花在ればこそ吾れも在り」という言葉からもよくわかります。本当に植物を愛した人だったんですね。また、展示の中に、牧野氏ゆかりの人々が作成した標本もありました。中でも楽しかったのは、果物や野菜の標本です。イチゴ、マンダリンオレンジ、スイカ、パイナップル、キュウリ、かぶなど色合いも形も美しくまるで絵画作品を見るようでした!実際にそれらを標本にするにあたり、立体的な果物や野菜をどのようにして平らにするのか、常に試行錯誤だそうです。そして「どの特徴を重視するか、どのように表現するかは人によって異なります」とありました。それらの標本は、「芸術作品」ともいえ、「採集者、作成の個性や思想が強く反映されている」そうです。確かに採集時期により、開花前だったりするなど、全く違ったものになりますね。今日の展示を見て、牧野富太郎という人の植物に対する一途な生き方、そして標本がもたらす多くの意味や意義(人々の暮らし、生活史、歴史、環境の変化などが標本からみえてくることなども含めて)を改めて考えさせられました。

マンダリンオレンジの標本です。甘い香りが漂ってきそうです!

マンダリンオレンジの標本です。甘い香りが漂ってきそうです!
2023年09月28日
クラスの盛り上がり!
先週から大学の授業が始まりましたが、担当科目の中で、大変盛り上がる授業があり、なぜなのかふと考えてみました。そのクラスは、学生数23名というこじんまりとした英語の関連科目なのですが、なんといってもクラスの雰囲気が、誰かが答を間違えたり、答に戸惑ったとしてもそれを皆で、暖かく、楽しく(‽)受け入れる姿勢だと思います。例えば、選択肢の問題で、4つの中から正しい答えを選ぶとき、一人の生徒が間違った答えをしたとします。 私の方では、”one more chance!"を与えますが、また間違えた答えが返ってきます。すると他の生徒たちが”Please give him one more chance!”とニコニコして私の方に頼んできます。そしてまたまた正解でない場合、答はあと一つしか残っていないわけですが、そんな時にも皆が一斉に”One more chance!”と笑いながら、言ってきます。当然、彼の次の答えは正解になります。そこでみんなで大笑い!! こんな調子です。また、今日は授業でShadowing(nativeの英語音声を聞き、その少し後を同じような発音、リズムで追いかけていくやりかた)に皆で取り組みました。なかなか難しくみんな四苦八苦!最初にスタートした生徒が緊張してしどろもどろに。そんな時みんなの大きな拍手!そこで楽しい笑いが!何人かの学生たちもtryしましたが、なかなかうまくできません。それでもすべての生徒たちに対して、クラスの皆がまたまた大きな拍手!こんな雰囲気になると学生たちの緊張もほぐれてきます。失敗やうまくできなくても大丈夫! という雰囲気になるのです。私も失敗は成功の素!間違えることは大事!間違えたらそこから覚えていけばいい!といつもクラスで言っています。間違えてもいいんだという雰囲気作りをこれからも心がけ、皆が楽しくクラスに参加してくれたらいいなと考えています。

南アフリカのgame reserveで出会った水牛さん。じっと見つめられてまるでhuman watchingしているようでした(笑)それにしても癒されます!

南アフリカのgame reserveで出会った水牛さん。じっと見つめられてまるでhuman watchingしているようでした(笑)それにしても癒されます!